「ボウリングボールって、どれも同じに見えるけど何が違うの?」そう感じたことはありませんか?実は、ボウリングボールは「選び方」でスコアも上達スピードも大きく変わる、非常に重要なアイテムです。重さ・素材・穴の形、さらには内部構造まで、プレイヤーのレベルや目的に合わせて最適な選択肢が存在します。本記事では、初心者から中上級者までが満足できるボール選びのすべてを、事実とデータに基づいて徹底解説します。
こんな人におすすめの記事:
- ボウリングを始めたばかりで、どのボールを選べばいいかわからない人
- マイボールを検討しているが、失敗したくない人
- 上達を目指す中で、もっと安定して投げたい人
- 素材や内部構造まで知って、こだわりたい人
- 自分や家族(子ども・女性・シニア)に合ったボールを探している人
目次
ボウリングボール、何を基準に選ぶ?最初に知っておくべきこと
ボウリングにおいてボール選びは、技術と同じくらい結果に直結する重要な要素です。特にスコアやフォームに悩んでいる人にとって、マイボールの導入は大きな分岐点になります。ここではまず、初心者が理解すべき基本情報と、ハウスボールとマイボールの違いを明確にします。
|
比較項目 |
ハウスボール |
マイボール |
|
所有形態 |
レーン設置の貸出用 |
自分専用 |
|
サイズ調整 |
不可(既成の穴) |
可(ドリル加工) |
|
素材 |
主にポリエステル |
高機能素材(ウレタン・リアクティブ等) |
|
軌道 |
直進しやすい |
回転や曲がりを調整可 |
|
スコアへの影響 |
初心者向け |
中級者以上に最適 |
道具選びの段階で、すでにスコア差は生まれています。

北野 優旗
「自分専用のマイボールを持つことで、握りやすさと回転が安定し、フォーム改善にもつながります。上達スピードが格段に早くなるので、ボウリングを本気で楽しみたい方は早めの導入をおすすめします!」
重さの選び方:持てる≠投げやすい
多くの初心者がやりがちなミスが、「持てる重さ=投げられる重さ」と誤解してしまうことです。しかし、実際にはフォームや筋力、スタミナまで考慮したうえで、自分に合ったボールの重さを選ぶ必要があります。重すぎるボールは疲れやすく、軽すぎるボールは安定性や回転力に欠けます。
適切な重さのボールを選ぶことが、安定したスコアとケガ予防の両方につながります。
体重の10分の1説は本当か?
「ボールは体重の約10分の1が目安」とよく言われます。たとえば体重60kgの人なら、6ポンド(約2.7kg)を選ぶのが基本…ですが、これはあくまで「目安」です。実際には筋力や投げ方、レーンの状況などが影響するため、絶対的な基準にはなりません。
「10分の1説」はあくまでスタートラインに過ぎない。
さらに重いボールはピンに与える衝撃が大きくなる一方で、握力や体幹が弱いとスムーズなリリースが難しくなり、かえってスコアが安定しなくなります。逆に軽すぎるとコントロールは良くなってもピンアクションが弱くなり、ストライク率が落ちる傾向にあります。
また、「片手で15秒間静止できるか?」という簡易テストを使って、自分にとって無理のない重さを知ることも可能です。15秒以上持っていられない場合は、明らかに重すぎると考えられます。
科学的根拠となる文献: Grip Strength: An Indispensable Biomarker For Older Adults(握力:高齢者にとって不可欠なバイオマーカー)
握力・疲労感・フォームから考えるベスト重量
最も理想的な重さは、「ゲーム終盤まで安定して投げられるか」にあります。1ゲームや2ゲームでは問題なくても、5ゲーム、10ゲームと続くときに疲れが出てミスが増える場合は、重すぎる証拠です。
「後半に崩れない重さ」こそが、自分に合った理想の重量だ。
握力だけでボールを持ち続けると手や腕に過度な負担がかかるため、指先・肩・背中まで使った「全身で持つ意識」が必要になります。フォームに合った重さであれば、自然と体全体で支える感覚がつかめてきます。
さらに、軽すぎるボールを選んでしまうと、手首の使いすぎでフォームが崩れたり、余計な力を入れてしまう癖がつきやすくなります。そのため、適切な重さを選ぶことで、技術的にもバランスの良い成長が可能です。
女性・子ども・シニア向けの重さ目安もチェック
以下に、性別や年齢に応じた目安の重さを表にまとめました。あくまで参考値としてご覧ください。
|
プレイヤー属性 |
体重目安 |
ボールの重さ |
|
小学生低学年(30kg以下) |
~30kg |
6~8ポンド |
|
小学生高学年~中学生 |
30~45kg |
8~10ポンド |
|
女性(体重50kg前後) |
45~55kg |
10~12ポンド |
|
男性(体重60kg以上) |
60~80kg |
12~15ポンド |
|
シニア(60歳以上) |
個人差あり |
8~12ポンド(関節負担を考慮) |
年齢や性別に関係なく「自分にとって快適な重さ」がベストである。

北野 優旗
「最初は軽めからスタートして、慣れてきたら徐々に重さを上げていくのが基本です。とくに成長期の子どもや、運動不足の大人は『無理しないこと』が何より大切です。」
穴サイズとスパン:親指が語る、あなたのフィット感
ボールを投げる際に「抜けが悪い」「すっぽ抜ける」といった違和感を感じたことはありませんか?それは、ボールの穴(フィンガーホール)のサイズや配置(スパン)が手に合っていない可能性が高いです。マイボールを選ぶうえで、もっとも重視すべき要素の一つがこのフィット感。たとえ重さや素材が合っていても、穴が合わないだけでケガやスコア低下につながってしまいます。
「穴が合っているかどうか」で、投球の安定感も安全性も決まるのです。
親指・中指・薬指の「脱出スムーズ」が成否を分ける
フィンガーホールは「握る」ためではなく、「リリースする」ためのもの。中指と薬指は奥までしっかり入り、親指は力まず自然に抜けることが理想です。この「抜けのスムーズさ」がスイングや回転に直結し、ストライク率にも明確な影響を与えます。
抜けが悪いと感じた瞬間、ボールは理想の軌道を描けなくなります。
ドリル(穴開け)は、手の大きさ・指の太さ・可動域などを元にミリ単位で調整されるため、プロショップでの測定は必須です。一般的には「コンベンショナルグリップ」と「フィンガーチップグリップ」の2種類があり、初心者は前者、中・上級者は後者を選ぶことが多いです。
|
グリップ形式 |
指の挿入 |
特徴 |
|
コンベンショナル |
第2関節まで入れる |
安定感があり初心者向け |
|
フィンガーチップ |
第1関節まで入れる |
回転がかかりやすく上級者向け |
とくに親指のホールは「ややきつめ」が理想。投げていくうちに汗や摩耗で緩んでくるため、最初からゆるめに開けてしまうと、フィット感が早期に失われます。プロはインサート(指穴の中に装着するゴム)を用いて調整することで、いつでも一定のグリップ力を保てるよう工夫しています。
また、「テープの使い方」もポイント。親指に貼るテープと、穴に貼るテープを使い分けて細かくフィット感を調整することができます。
スパンとブリッジ調整でケガ防止&安定感アップ
「スパン」とは中指と薬指の間の距離で、「ブリッジ」とはその2つの穴の間隔を指します。これらが適切でないと、腱や靭帯に余計な負担がかかり、腱鞘炎や関節炎の原因になってしまうのです。
「しっくりこないスパン」は、ケガとミスのもと。
スパンが短すぎると握力に頼るため疲れやすくなり、逆に長すぎると指が無理に引っ張られてケガのリスクが高まります。また、ブリッジが狭すぎると指がぶつかり、広すぎると力が分散してしまいます。
ドリルの際には以下のような項目が測定されます:
- 指の長さと太さ
- 手の甲の形状
- 握力や柔軟性
- 投げるスタイル(ストレートorカーブ)
- 利き手
すべてを考慮したうえで最適なホール設計を行うことで、無理のない自然なリリースが可能になります。初心者こそ、こうした計測とドリルを経験することで「ボールが手に吸い付く感覚」を得られます。

北野 優旗
「フィット感の悪いボールで練習を続けると、フォームまで崩れてしまいます。手の小さな方や指が柔らかい方は、必ず専門ショップでの測定をおすすめします。フォームとボールのフィットはワンセットです。」
素材とカバーストックの種類:ボールの個性を知る
ボウリングボールの表面素材(カバーストック)は、ボールの性格そのものを決める重要な要素です。軌道の安定性、曲がり方、レーンのオイルとの相性まで、すべてがこの素材に左右されます。特に、初心者が選ぶべき素材と中上級者が使う素材は全く異なります。
素材の選択は「ただの見た目」ではなく、投球の結果に直結する技術的選択なのです。
ポリエステル・ウレタン・リアクティブレジンの性能差
カバーストックの主な種類は、大きく分けて3つ。それぞれに特性があり、選ぶ素材によってボールの挙動が大きく変化します。
|
素材 |
特徴 |
おすすめユーザー |
価格帯 |
|
ポリエステル(プラスチック) |
直進性が高く曲がりにくい |
初心者・スペア狙い用 |
安価 |
|
ウレタン |
ほどよく曲がる・レーンへの影響が少ない |
中級者・トーナメント向け |
中価格帯 |
|
リアクティブレジン |
回転・曲がりが強くパワーのある投球に最適 |
上級者・競技者 |
高価 |
初心者には直進性が高く扱いやすい「ポリエステル」がベスト。
ポリエステルは摩擦が少ないため、レーンのオイルパターンに影響されにくく、まっすぐ投げたい人に最適です。一方で「曲げたい」「回転をかけたい」という人は、ウレタンまたはリアクティブレジンを選ぶべきですが、これにはコントロール技術も必要になります。
リアクティブレジンは摩擦力が非常に高く、回転やフックがかかりやすい一方、レーンの状況によっては暴れすぎてしまうリスクも。これを扱いこなすには、投球精度と知識が求められます。
科学的根拠の文献:What Exactly Is Rs and Ra In Bowling Balls and Does It Matter(ボウリングボールのRsとRaとは一体何なのか?そしてそれは重要なのか?)
曲がりやすさ・レーンへの反応性を左右する要素
素材だけでなく、カバーストックの「仕上げ」や「表面粗さ」もボールの挙動に大きく影響します。粗いサンディング加工がされているほどオイルに引っかかりやすくなり、滑りにくく、より強く曲がる傾向にあります。
「仕上げの違い」が、同じ素材でも全く異なる軌道を描かせる。
ボール表面の仕上げには以下のようなパターンがあります:
- ポリッシュ仕上げ:表面がツルツルで直進性が高く、乾いたレーンで効果的。
- マット仕上げ(サンディング):摩擦が大きく、曲がりが強く出る。オイルが多いコンディション向き。
- 粒度指定仕上げ(例:500グリット、1000グリットなど):表面の粗さを調整して、オイル吸収性やフックの早さを制御可能。
素材と仕上げの組み合わせにより、同じ投球でも全く異なる結果が生まれるのです。特に競技者は、複数の素材・仕上げのボールを用意して、レーン状況に応じて使い分けるのが一般的です。

北野 優旗
「初心者はまず、シンプルに直進性重視のボールで基礎を固めましょう。いきなり高性能なリアクティブを使うと、かえってフォームが崩れやすくなります。慣れてきたらウレタン、最終的にリアクティブと、段階的にレベルアップを図るのがおすすめです。」
コア形状とRG値:ボールの「中身」が軌道を決める
ボウリングボールの中心にある「コア(重心構造)」は、外側からは見えないながらも、投球軌道や回転数、フックのタイミングに大きな影響を与える重要な要素です。さらにRG(回転半径)という物理的な値によっても、ボールの動きは細かく変化します。
「目に見えないコア構造」こそ、ボール性能の本質が詰まっている。
対称・非対称、ショートRGとロングRGの違いとは?
ボウリングボールのコアには「対称コア(シンメトリック)」と「非対称コア(アシンメトリック)」があります。それぞれに回転のかかり方や曲がりのタイミングに大きな差があり、投球スタイルや目的に応じた選択が必要です。
|
コアタイプ |
特徴 |
おすすめプレイヤー |
|
対称コア |
バランスが良く安定性に優れる |
初心者~中級者 |
|
非対称コア |
フックの立ち上がりが早く、曲がりが強い |
上級者・競技者向け |
安定性を求めるなら「対称コア」、攻撃力を求めるなら「非対称コア」。
また、RG値(Radius of Gyration:回転半径)はボールがどれだけ早く転がり始めるかの指標で、低いRG(Low RG)ほど早く転がり始め、高いRG(High RG)はスキッド(滑り)が長く続きます。
|
RG分類 |
回転開始タイミング |
向いているスタイル |
|
Low RG(2.46~2.50) |
早い |
パワーボウラー・オイル多め |
|
Medium RG(2.51~2.54) |
標準 |
バランスタイプ |
|
High RG(2.55以上) |
遅い |
スピードボウラー・ドライレーン |
たとえば、レーンのオイルが多いときにはLow RGのボールが早く転がって安定しやすく、逆にオイルが少なくドライな状況ではHigh RGの方がレーンを滑って奥で鋭くフックする形になります。
どんなコアがどう曲がる?物理特性で投球が変わる
コアの形状は、まるで宇宙船のような複雑な構造をしているものも多く、これが回転のタイミングや回転軸のズレ(プリセッション)に影響を与えます。非対称コアは軌道を強く変化させることができるため、レーンの奥で強く曲げたい場面に有効です。
コアの重心移動こそが、回転の変化と曲がり幅の鍵となる。
たとえば、ピラミッド型や楕円型のコアは回転軸の傾きが変わりやすく、結果として投球に「バックエンドの強さ」が生まれます。一方、円筒型やシンプルな対称コアは、一定のスムーズな軌道を描くため、再現性を重視する選手に向いています。
また、慣性モーメント(Moment of Inertia)も重要なポイントで、これが高いほど回転が安定しやすく、低いほど変化が大きく出やすくなります。慣性モーメントはRG値やコアの質量配分に影響され、ボールによって異なります。
「コアがどう働いているか」を正しく理解することで、プレイヤーはより自分のプレイスタイルにマッチしたボールを選べるようになります。

北野 優旗
「初心者の方には“対称コア+Medium RG”のようなバランス型がおすすめです。扱いやすく、基本的なフォームや回転をしっかり身につけられます。非対称コアやLow RGは、その特性を活かす技術が身についてから使いましょう。」
レーンコンディションと相性のよいボール選び
ボウリングはただボールを投げるだけのスポーツではありません。スコアアップの鍵は、「その日のレーンコンディションに合ったボールを選べるかどうか」にも大きく左右されます。特に、レーンに塗布されたオイルの量や配置によって、同じボールでも全く異なる軌道を描くのです。
レーン状況に合ったボール選びができれば、思い通りのフックとストライク率が手に入ります。
オイルパターンの読み方:ドライ?ミディアム?ヘビー?
レーンには必ず「オイル」が塗られており、この量や長さによってボールの摩擦力、すなわち「曲がりやすさ」が大きく変化します。主に以下の3つのパターンが存在し、それぞれに適したボール特性があります。
|
オイルパターン |
特徴 |
おすすめのボール特性 |
|
ドライ(乾いている) |
摩擦が大きくすぐに曲がる |
表面ツルツルのポリッシュタイプ/High RG |
|
ミディアム |
標準的なコンディション |
バランスタイプ(リアクティブ/Medium RG) |
|
ヘビー(オイルが多い) |
摩擦が少なく直進しやすい |
サンディング加工/Low RG/非対称コア |
「オイルが多い=滑る」ため、曲がりが遅くなるという基本を押さえよう。
例えば、家庭用ボウリング場では「ミディアム」または「ややドライ」なことが多く、リアクティブボールのポリッシュ仕上げが扱いやすいでしょう。一方、プロ仕様のトーナメントではヘビーオイルコンディションが採用されることが多く、ボール選びを間違えると全く曲がらず苦戦します。
特に初心者は「今日はまっすぐ行かないな…」と感じたら、レーンが乾いてきた(ドライ化)と考えてOKです。そういったときに、摩擦の少ないボールに持ち替えることができれば、コントロールミスを防げます。
科学的根拠の文献:Understanding Lane Friction(車線の摩擦を理解する)
ボール表面加工(ポリッシュ・サンディング)の調整術
同じボールでも、表面加工によってその性格は大きく変わります。つまり、「素材」と「加工」の組み合わせが戦略の幅を広げてくれるのです。代表的な表面仕上げには以下のような違いがあります。
- ポリッシュ加工:滑りやすく、レーン奥で急激に曲がる。ドライ気味なレーンに最適。
- サンディング(マット)加工:レーン序盤から摩擦が発生し、手前で曲がり始める。オイルが多いヘビーレーンで有効。
- 粒度コントロール:仕上げ時に使用するグリット(400、1000、2000など)を調整することで、より細かく摩擦を制御。
同じ素材でも、仕上げ加工によって全く別の「性能」を持ったボールに変わる。
レーンに合わせてボールの表面を再仕上げすることを「リサーフェス」と呼びます。競技ボウラーは大会前に必ずこれを行い、レーンに合わせたフックの調整を実施します。アマチュアでも、マイボールを購入したら定期的なメンテナンスやリサーフェスを行うことで、性能を維持しやすくなります。
また、「ストーム」や「モーティブ」などのブランドでは、表面仕上げの特徴をモデルごとに公開しており、選ぶ際の重要な参考になります。

北野 優旗
「ボールの素材や重量に目が行きがちですが、レーン状況に合うかどうかをチェックする習慣が何より大事です。ポリッシュ、マット仕上げのボールを1個ずつ持っておくだけでも、適応力は大きく変わります。」
初心者と中・上級者のボール選び、何が違う?
ボウリングボール選びにおいて、プレイヤーのレベルによって最適な選択肢が大きく異なります。初心者が中・上級者向けのボールを使っても、かえってフォームが乱れたりスコアが下がることがあるため、自分のレベルに合わせた選択が大切です。
「ボールの進化はスキルとともに」??それが上達の王道です。
初心者はまず「直進性重視」でOK?
初心者の最大の課題は、「狙ったところにボールを投げる」ことです。そのためには、余計な回転や変化が起きない「直進性の高いボール」がベストです。ポリエステル素材やコンベンショナルグリップのマイボールなど、操作性が高く、安定して投げられるものが理想的です。
「まっすぐ転がす技術」が、すべての基本となる。
初心者は「曲げようとしない」「軽すぎず、重すぎない重量」「正しいフィンガー配置」で、フォームを安定させることに集中するのが最優先。特に以下のようなボールは初心者に適しています。
- ポリエステル素材(低摩擦):直進性が高く、コントロール練習に最適
- 対称コア:安定性が高く、意図しない曲がりを抑えられる
- Medium RG:スキッドと回転のバランスが良く、扱いやすい
- コンベンショナルグリップ:フィンガーチップよりも指に負担が少なく、ミスが少ない
このような仕様でマイボールを作ることで、初心者でも安定したスイングと投球が可能になります。最初からリアクティブレジンなどを選ぶと、コントロールを失いやすく「ボールに振り回される」状況に陥りがちです。
上級者が求める「攻め」のボールとは
一方、経験を積んだ中級者や上級者になると、求めるものは「より大きなフック」や「レーンごとの戦略的投球」です。そのため、素材・コア・表面仕上げなどにこだわり、自分のスタイルに合った特化型ボールを使用します。
「状況を読み、武器を使い分ける」ことが上級者の流儀。
例えば上級者は以下のような要素を重視します:
- 非対称コア+リアクティブレジン:回転と曲がりの最大化
- Low RG:早い転がり出しで安定したフックタイミング
- サンディング加工:オイルの多いコンディションで早い摩擦を実現
- フィンガーチップグリップ:回転数を最大化し、ストライク率アップ
また、上級者は1球種に頼るのではなく、状況別に複数のボールを使い分ける「ボールラインナップ」を構築しています。これにより、レーンのオイル変化にも柔軟に対応できます。
さらに、トーナメントなどで活躍するプロ選手は「レーンリーディング」を行い、オイルの配置に応じてその場で最適なボールや投球ラインを変えています。彼らにとってボールは「表現の道具」であり、「点を取るための戦略装備」なのです。

北野 優旗
「初心者の方は、まず1球で十分です。ただし、自分のレベルが上がってきたと感じたら、素材・コア・加工を段階的に変えていくことで“ボールでプレーする感覚”を楽しめるようになります。これはスコアだけでなく“上達する喜び”そのものですよ。」
コストと価値:高いボール=うまくなる?
マイボールの購入を考えたとき、誰もが一度は気になるのが「価格と性能のバランス」です。安いボールでうまくなれるのか?それとも高額モデルこそがスコアアップの鍵なのか?結論から言えば、「自分に合っていない高価なボールは宝の持ち腐れ」です。
価格よりも「適合性」こそが、投球パフォーマンスを左右する最大要素です。
価格帯別の違いを徹底比較
まずは価格帯ごとの一般的な性能や特徴を整理してみましょう。
|
価格帯 |
相場(円) |
主な素材/構造 |
対象ユーザー |
特徴 |
|
~1万円 |
中古品・エントリーモデル |
ポリエステル・一部ウレタン |
初心者・入門者 |
安価で扱いやすいが性能は抑えめ |
|
1万~2.5万円 |
一般的なリアクティブ・ウレタン |
対称コア/リアクティブ素材 |
初心者~中級者 |
コスパが良く多くの用途に対応 |
|
2.5万~4万円 |
高性能リアクティブ |
非対称コア・表面加工多彩 |
中級者~上級者 |
曲がり強め、戦術向き |
|
4万円以上 |
プロ用ハイエンドモデル |
非対称+複雑コア・特化加工 |
上級者・競技者 |
高精度な軌道制御、レーン特化型も |
価格は性能の目安にはなるが、レベルに合わなければ効果は限定的です。
たとえば初心者がいきなり4万円のハイエンドモデルを買っても、その性能を活かす投球技術がなければ真価を発揮できません。逆に、中級者以上が安価なエントリーモデルを使い続けると、スキルの伸びが頭打ちになることも。
購入時には「将来どこまで上達したいか」「頻度や目的」「レーン環境」などを考慮し、投資のバランスをとることが重要です。
科学的背景:Your Complete Guide to Bowling Equipment: FAQs and Expert Tips(ボウリング用品の完全ガイド:よくある質問と専門家のヒント)
コスパ重視ならこのラインが狙い目
「できるだけ出費は抑えたいけど、性能も妥協したくない」という方には、2万円前後のミドルクラスモデルがもっともおすすめです。このクラスでは、
- リアクティブレジン素材でフックが可能
- 中~高摩擦のカバーストックで汎用性あり
- 対称コアで安定感があり扱いやすい
といった特徴があり、初めてのマイボールにも、技術の底上げにも最適です。ブランドで言えば「STORM」「EBONITE」「MOTIV」などのミドルレンジモデルは評価も高く、人気があります。
1ランク上のボールが、技術の壁を破るキッカケになる。
一方で、予算に余裕がある方は2個目・3個目のボールとして「コンディション別」に複数用意すると、レーンに対する対応力が飛躍的にアップします。特に大会やリーグに参加する予定がある方には必須戦略です。

北野 優旗
「最初のマイボールは“自分に合っているかどうか”が最優先。安くても自分にジャストフィットすれば、それが最高の1球になります。逆に“値段に見合った投球技術”を持っていないうちは、高級ボールも宝の持ち腐れですよ。」
マイボール作成の流れとショップ選び
ボウリングをより本格的に楽しむなら、「マイボール作成」は避けて通れない重要なステップです。ただし、適当に選んでドリル(穴開け)してしまうと、せっかくのマイボールも逆効果になる恐れがあります。成功のカギは、「信頼できるショップ」と「正確なフィッティング」にあります。
マイボールは“ただの道具”ではなく、あなたのプレースタイルを支える最強の味方になります。
ドリル前の採寸とカウンセリング
マイボールの作成は、まず「手の測定」からスタートします。これは「フィンガーサイズ」だけでなく、「スパン(指の距離)」「手首の可動域」「投球スタイル」などを総合的にチェックするプロセスです。
たった数mmのズレが、投球精度や安全性を大きく左右する。
採寸では以下のような点が確認されます:
- 親指・中指・薬指の直径(mm単位)
- 指の曲がりやすさ・柔軟性
- 手のひらの厚さや形状(甲高・扁平など)
- 手首の可動域やスナップのクセ
- 投球スタイル(ストレート・カーブ・スピナー)
- 利き手や投球フォームの特徴
この情報をもとに、ドリル担当者が穴の「角度」「深さ」「間隔(スパン)」をミリ単位で設計します。さらに、「コンベンショナルグリップ」か「フィンガーチップグリップ」かも、プレイヤーのレベルや目的に応じて選ばれます。
また、親指ホールに使う「インサート」や「テープ」も、握力やリリースの癖に合わせて提案されることが多く、プロ仕様のカスタマイズが可能です。
科学的参考資料:Biomechanical Analysis of a Bowling Swing(ボウリングスイングの生体力学的分析)
信頼できるプロショップの見分け方
一口にプロショップといっても、知識や技術には差があります。とくに「ショップの規模が大きい=技術力が高い」とは限りません。信頼できるショップを選ぶには、以下のようなチェックポイントを参考にしましょう。
プロショップ選びの重要ポイント:
- 測定器具が豊富か(ノギス・スパン測定器・ボールバランサーなど)
- ドリラーがJBC(日本ボウリング連盟)やIBPSIA(国際プロショップ協会)の認定を受けているか
- 使用ボールの説明が丁寧で、納得するまでカウンセリングしてくれるか
- 投球フォームを動画で見てからアドバイスしてくれるか
- 「仮ドリル」や「試し投げ」ができる環境があるか
- 過去の顧客レビュー・口コミが良好か
「ただ売るだけ」の店ではなく、「一緒に最適解を見つけてくれる」プロがいる店を選ぼう。
また、近くに信頼できるショップがない場合は、ボウリング場と併設された施設よりも、専門ショップの方が技術に長けている傾向があります。オンラインでの評判やSNS、ボウリング大会での露出実績なども確認しておくと安心です。

北野 優旗
「最初のマイボールは“成功体験”が大切です。信頼できるショップ選びを妥協しないことが、上達の最短ルートになります。採寸から仕上げまで、丁寧に向き合ってくれるスタッフを見つけることが重要です。」
よくある質問
ボウリングボールの選び方に関して、実際に多くの方から寄せられる疑問を厳選してお答えします。特に初心者がつまずきやすいポイントや、購入後に後悔しがちな点を中心に解説していきます。
Q1: 初心者でもマイボールを買うべき?
答え:はい、むしろ初心者こそマイボールをおすすめします。
なぜなら、ハウスボールはサイズや重さ、穴の位置が自分に合っていないことが多く、フォームが崩れたり、変なクセがついてしまう可能性があるからです。最初からフィット感のあるボールで練習することで、安定した投球と正しいフォームを身につけやすくなります。
「最初の一球」で、上達のスピードは大きく変わる。
Q2: ボールの寿命ってどれくらい?
答え:使用頻度やメンテナンス状況によりますが、一般的に2~5年が目安です。
リアクティブレジンのボールはオイルを吸収しやすく、吸いすぎるとフックの効きが悪くなってきます。定期的な「オイル抜き(リサーフェス)」や表面加工のメンテナンスを行うことで、性能を長持ちさせることが可能です。
Q3: 手が小さい・握力がない人におすすめは?
答え:軽量で、かつ親指ホールがタイトすぎない設計のマイボールがおすすめです。
女性や子ども、高齢者の方には、10~12ポンドの軽量タイプで、コンベンショナルグリップのボールが使いやすく安全です。ドリル時に手の大きさや握力を考慮してもらうことで、適切なフィット感を得られます。
「手の小ささ」はハンデではなく、設計でカバーできる。
Q4: 中古ボールってどうなの?
答え:安価で始めたい方にはおすすめですが、リスクもあります。
中古ボールは値段が安く、入門には向いていますが、前使用者の手に合わせた穴開けがされており、必ずしもあなたに合うとは限りません。また、オイルを吸いすぎて劣化しているものも多く、パフォーマンスが落ちている可能性もあります。
信頼できるショップで「再ドリル可能」「表面加工済み」のものを選べば安心です。
Q5: スペアボールとメインボールって両方必要?
答え:中級者以上なら2個持ちが基本です。
スペア用のポリエステルボールは「まっすぐ進む」特性があるため、ピンが1~2本だけ残った場合の精密なコントロールに適しています。リアクティブメインボールでフックを多用する人は、スペア用ボールを別途持つことでスコアが安定します。
まとめ
本記事では、「ボウリングボール 選び方」に関するあらゆる知識を網羅的に解説してきました。初心者が最初の1球をどう選ぶかから、上級者が軌道をコントロールするためのボール戦略まで、ボール選びの正解は一つではなく、「目的・技術・環境」によって変わるということをご理解いただけたと思います。
ボウリング上達の第一歩は、「自分に合ったボールを知ること」から始まるのです。
あなたのレベルに応じた最適解を選ぼう
初心者であれば、まずは直進性の高いポリエステル素材で投球フォームを安定させることが第一歩です。手のサイズや握力に合った穴開け(ドリル)を施したマイボールを持つことで、無理なくスキルアップが図れます。
中級者以上になれば、リアクティブレジン素材や非対称コアなど、より高度な特性を持ったボールで「攻め」のプレイスタイルを追求していけます。複数のボールを状況に応じて使い分けることで、スコアの伸び率が劇的に変わるでしょう。
見た目や価格だけで選ばない
価格が高ければ高性能というわけではなく、あくまで「自分に合っているか」が最も重要です。マイボール作成では必ず信頼できるショップを選び、丁寧な採寸とアドバイスを受けることが、長く快適にプレーするためのカギになります。
- 初心者には: 重すぎず、まっすぐ進むボール+コンベンショナルグリップ
- 中級者には: 中程度のフック+対称コア+リアクティブ素材
- 上級者には: コンディション別の複数ボール+非対称コア+仕上げ調整
最後に伝えたいこと
ボウリングは「道具のスポーツ」であり、シューズ・フォーム・ボール、すべてがスコアや上達スピードに影響を与えます。中でも「ボール」は最も重要なファクターであり、単なる球体ではなく、あなたのスキルを引き出す“相棒”です。
一度自分専用のボールを持てば、その感覚は「手に吸い付くような投げ心地」として記憶に刻まれることでしょう。そして、その1球が、あなたのボウリング人生を大きく変えてくれるはずです。
「このボールでなら勝てる」と思える1球を、ぜひあなたの手に。
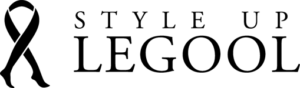



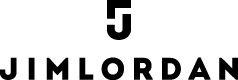





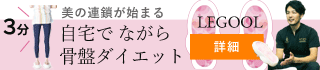
コメント