マラソンと筋トレ、一見すると正反対のように見えるかもしれません。しかし、近年の研究や実践例から「筋トレを取り入れたランナー」のパフォーマンスが著しく向上していることが明らかになってきました。長距離を走るために必要な“持久力”に加え、実は“筋力”が大きな鍵を握っているのです。本記事では、マラソン初心者から経験者まで幅広く対応した「筋トレ導入の完全ガイド」をお届けします。
こんな人におすすめの記事:
- 筋トレとマラソンの両立に不安がある人
- フルマラソンの記録が伸び悩んでいる人
- 怪我が多くて改善策を探している人
- 自宅トレーニングでも結果を出したい人
- ダイエット目的でマラソンを始めた人
目次
マラソン初心者のための筋トレ入門:まず何から始める?
マラソンを始めたばかりの人にとって、「筋トレは必要なの?」「走るだけじゃダメ?」という疑問はよくあるものです。結論から言えば、筋トレを取り入れることでフォームが安定し、怪我のリスクを減らし、結果的に長く速く走れるようになります。 特に初心者の場合は、走る距離やスピードを優先しがちですが、まずは筋肉の土台を整えることが最優先です。
走る前に鍛えるべき?筋トレの基本スタンスを解説
マラソン初心者が筋トレを導入する際には、いくつかの重要なポイントがあります。まず、筋トレの目的は「筋肥大」ではなく「機能性の向上」にあります。つまり、体を大きくするためのトレーニングではなく、走るために必要な筋肉のバランスと耐久性を育てるものです。
筋トレによってフォームの崩れを防ぎ、走行時の効率が飛躍的にアップします。 具体的には、ランニング中の着地時に生じる衝撃を和らげる「膝まわりの筋肉」や、姿勢維持に不可欠な「体幹部」の強化が挙げられます。
多くの初心者は「筋トレ=ハードルが高い」と感じますが、最初は1日10分のトレーニングでも十分効果が出ます。フォームや回数を重視して、負荷を少しずつ増やしていくことで安全に筋力アップを目指しましょう。
- 筋力不足による疲労蓄積:初心者が抱えやすいのは、ふくらはぎや太ももの筋力不足による後半の失速。これを防ぐために、スタート時から筋力強化が重要になります。
- 体幹の弱さによる姿勢崩れ:フォームの乱れはすべてのパフォーマンス低下につながります。背骨や骨盤を支える腹筋・背筋の強化がカギ。
- 膝・足首の怪我予防:関節の安定性は筋肉で守られています。弱いまま走ると、腱や靭帯を痛めやすくなります。
フォームと筋力はマラソンの基礎体力です。

北野 優旗
筋トレを始めるときは「全身をまんべんなく」ではなく、まず「走る動作に関わる筋肉」に集中しましょう。走る動きの中で多く使う部位(大腿四頭筋、ハムストリングス、体幹)から鍛えると、効果を実感しやすくなります。
マラソンに効く筋トレ種目ベストガイド
の本文を作成していきます。
マラソンに特化した筋トレを行うことで、パフォーマンスの向上だけでなく、怪我の予防や疲労軽減にも大きな効果が期待できます。走る動作に必要な筋群を意識的に鍛えることで、エネルギーの消費効率が高まり、より長く、より速く走ることが可能になります。特に下半身と体幹は、マラソンにおいて最も重要な筋肉群です。 以下の筋トレ種目は、多くのマラソン選手やトレーナーが推奨しており、科学的にも効果が裏付けられています。
下半身強化の王道:スクワットとランジの使い分け
スクワットとランジは、下半身を効果的に強化できる基本中の基本の種目です。マラソンに必要な筋持久力と衝撃吸収能力を高めるのに適しており、走行時の「ブレない脚づくり」に直結します。
スクワットは“走る力の根幹”となる太もも・お尻・ふくらはぎの筋群をまんべんなく鍛える万能種目です。
|
種目 |
主なターゲット |
目的 |
ポイント |
|
スクワット |
大腿四頭筋・臀筋・ハムストリング |
全体的な脚力強化 |
背筋を伸ばし、膝がつま先より前に出ないように |
|
フロントランジ |
大腿四頭筋・臀筋 |
片脚でのバランス強化 |
一歩踏み出す幅を大きく取るとお尻の刺激アップ |
|
サイドランジ |
内転筋・臀筋中部 |
横方向の安定性向上 |
体重を真横に乗せる感覚を大切に |
|
ブルガリアンスクワット |
臀筋・ハムストリング |
片脚の筋力差是正 |
膝が内側に入らないよう意識 |
どの種目も、週2~3回、10~15回×2~3セットを目安に行いましょう。無理な回数ではなく、「正しいフォームを意識しながら効かせる」ことが最重要です。

北野 優旗
スクワットとランジを行うときは、できるだけ「ゆっくりした動作」を心がけましょう。反動を使わず、筋肉で体をコントロールすることで、怪我を予防しながら効果を高めることができます。
参考論文:The effects of strength training on distance running performance and running injury prevention
フォーム安定と持久力に効く体幹トレーニング
の本文を作成します。
ランニング中に体が左右にブレたり、後半にフォームが崩れてしまうのは、体幹の筋力が不足しているサインです。マラソンにおいて体幹の強さは「安定したフォーム」「呼吸の効率化」「疲労の軽減」など、あらゆる面で重要な役割を果たします。体幹が安定すると、走りのロスが減り、結果的にタイムも安定して伸びていきます。
体幹とは、単に「腹筋」だけでなく、腹横筋・腹斜筋・背筋・骨盤周辺のインナーマッスル全体を指します。これらを鍛えることで、走行中の衝撃吸収や力の伝達がスムーズになり、フォーム維持が可能になります。
以下は、マラソンランナーに効果的な体幹トレーニングの代表例です。
- プランク系トレーニング
- フロントプランク:腹横筋を中心に体幹全体に効く
- サイドプランク:腹斜筋と骨盤の安定に有効
- プランク with リーチ/レッグリフト:動的要素を加えて実践的な安定力を養う
- ダイナミック体幹トレーニング
- バードドッグ:背筋と腹筋を同時に動かすことで連動性を高める
- マウンテンクライマー:体幹の安定を維持しながら心拍数もアップ
- Vシットアップ:腹直筋と腸腰筋を同時に鍛える高難度種目
- 体幹と股関節の連動強化
- グルートブリッジ(ヒップリフト):骨盤と脊柱の連動性を養う
- デッドバグ:体幹を動かさずに手足を独立して動かす高精度トレーニング
体幹が強いと、長時間にわたり軸のブレない走りが可能になります。
初心者はまず30秒~1分間の静止系プランクから始め、週に2~3回を目安に取り組んでみてください。フォームの崩れを防ぐことで、ランニングによる慢性的な疲労や故障を防止できます。
また、動的体幹トレーニングはウォームアップやクールダウンにも適しており、継続しやすい点もメリットです。できれば、体幹メニューは「走る前後」のルーティンに組み込むと効果的です。

北野 優旗
体幹トレーニングの効果は“派手さ”ではなく“継続”にあります。たとえ1日5分でも、毎日行うことで大きな差が生まれます。走る前のウォームアップとして組み込むと、怪我予防にもつながります。
怪我予防に必須!ハムストリングと腸腰筋へのアプローチ
の本文を作成いたします。
マラソンにおいて最も注意すべきトラブルの一つが「慢性的な故障」です。特にハムストリング(太もも裏)と腸腰筋(股関節周辺のインナーマッスル)は、走行動作における“推進力の要”ともいえる重要な筋肉であり、鍛え方やケアの方法を間違えるとパフォーマンスの低下や怪我に直結します。
腸腰筋とハムストリングの柔軟性と筋持久力が、長距離ランナーの走力を左右します。
ハムストリングは足を後ろに蹴り出す動作を担い、腸腰筋は足を前に出す動作に関与します。これらの筋肉が弱かったり、硬くなっていると、フォームが崩れ、膝や腰への負担が増加します。長時間のランニングではこの差が顕著に現れます。
以下に、マラソンランナーに推奨されるトレーニングとストレッチをまとめました。
|
種目 |
対象筋 |
種類 |
ポイント |
|
ヒップヒンジ |
ハムストリング |
トレーニング |
腰を丸めずに股関節から前傾する |
|
レッグカール(自重 or マシン) |
ハムストリング |
トレーニング |
反動を使わずゆっくり行う |
|
ニーレイズ |
腸腰筋 |
トレーニング |
背筋を伸ばしたまま膝を引き上げる |
|
ランジ with ツイスト |
腸腰筋・体幹 |
トレーニング |
上半身をひねることで腸腰筋と腹斜筋を同時刺激 |
|
ハムストリング・ストレッチ |
ハムストリング |
ストレッチ |
太ももの裏にじわっと伸び感があればOK |
|
開脚ヒップフレクサーストレッチ |
腸腰筋 |
ストレッチ |
骨盤を前傾させて股関節を伸ばすのがコツ |
これらのトレーニングは、筋肉の「使える強さ」と「使える柔軟性」の両方を引き出すことが目的です。特に腸腰筋は、見落とされがちですが、走行時の膝上げ・推進力の軸となる非常に重要な部位。意識的に鍛えることで、「地面を押す力」が劇的に変化します。
ハムストリングも「筋力」だけでなく「滑走性(筋膜の動きやすさ)」を意識し、ストレッチやフォームローラーなどを活用することが望ましいです。

北野 優旗
ハムストリングと腸腰筋は、使うだけでは不十分です。「鍛える→伸ばす→休める」の3ステップがセットであるべきです。とくに腸腰筋は深層にあるため、丁寧にケアする意識が重要。ストレッチ後のドリル(ニーリフトやハイニー)を習慣化すると良いですよ。
の本文を作成していきます。
「どんな筋トレを、どのくらい、どう組み合わせればいいのか?」は、マラソンランナーが最も悩むテーマの一つです。筋力を強化しながら、持久力やスピードを落とさずにトレーニングを組み合わせるには、目的に応じたメニュー設計とスケジューリングが非常に重要です。
特に、筋トレとランニングは「併用するタイミング」や「負荷の調整」によって効果が大きく変わってきます。疲労が蓄積するばかりのやり方では逆効果になってしまうため、走力アップに直結するような効率的な筋トレ戦略が必要です。
週何回が最適?ランと筋トレの黄金バランス
初心者~中級者ランナーの場合、筋トレは週2回が理想的な頻度です。それ以上行うと疲労が抜けづらくなり、ランのパフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性があります。 以下は週単位でのトレーニングプラン例です。
例:週4日トレーニングする場合のスケジュール
- 月曜:休養(またはストレッチ+軽い体幹)
- 火曜:スピード走+下半身筋トレ(スクワット系)
- 水曜:ジョグ+上半身 or 体幹中心の筋トレ
- 木曜:完全休養
- 金曜:ビルドアップ走+体幹ドリル(プランクなど)
- 土曜:自重筋トレ or 可動域トレ
- 日曜:ロング走(15~20km)+ストレッチでケア
このように、「強度の高いランの直後に筋トレを組み合わせる」「筋トレの翌日はランの強度を落とす」など、疲労コントロールと目的別の配置がポイントです。
筋トレの時間は、1回あたり30分以内でOKです。走力に直結する大筋群(脚・体幹)を中心に、フォームを意識した丁寧な動作を心がけましょう。
初心者ランナーにおすすめのシンプル筋トレメニュー
「いきなり複雑な種目は無理」「ジムに行く時間がない」という方でも安心して取り組める、自宅OK・器具不要の筋トレメニューを紹介します。
- 月:スクワット20回×2セット+プランク30秒×2セット
- 水:ランジ左右15回×2+サイドプランク各30秒×2
- 金:グルートブリッジ15回×2+デッドバグ10回×2セット
- 日(走らない日):ブルガリアンスクワット左右10回+Vシットアップ20回
大切なのは“続けられる設計”にすること。
この程度の負荷でも、継続すれば数ヶ月で走力が変わってきます。フォームを崩さず行い、トレーニングノートなどに記録を取っておくとモチベーション維持にもつながります。
大会前はどうする?直前期・直後期の筋トレ戦略
レースが近づいてくると、「筋トレを減らすべきか?」「筋肉痛を避けるには?」などの疑問が出てきます。大会3週間前からは、筋肥大目的の高負荷トレーニングは避け、可動域拡大・動作のスムーズ化を目的とした軽めの筋トレに移行しましょう。
- 大会3週間前:通常通り(中~低負荷、回数重視)
- 大会2週間前:下半身は自重中心に移行(ストレッチ多め)
- 大会1週間前:体幹中心の軽い筋トレのみ。筋肉痛になるような負荷は避ける
- 大会前日:完全休養、またはストレッチのみ
大会直後1週間は「完全休養+ケア」の週とし、無理に筋トレは入れないようにしましょう。腸腰筋や足裏、ハムストリングなどをケアしながら、次のトレーニング期への準備を進めます。

北野 優旗
「筋トレは週に何回やればいいですか?」という質問をよく受けますが、大切なのは「ランとのバランス」と「疲労管理」です。ランの質が下がっては本末転倒なので、体調を見ながら、少しずつ頻度や強度を増やすのが成功のコツです。
筋トレとランニング、どっちを先にやるべき?科学が教える順序論
の本文を作成します。
「筋トレしてから走る?それとも走ってから筋トレ?」――これはマラソンランナーが陥りがちな“順番迷子”の悩みです。実はこの順序、目標によって“正解”が変わるというのが最新のスポーツ科学の答えです。
目的に応じて「筋トレ先行」か「ランニング先行」を使い分けることで、効率的なトレーニングが可能になります。
研究によると、筋トレと有酸素運動を組み合わせる「コンカレント・トレーニング(Concurrent Training)」では、両者の順番が成果に与える影響が明確に示されています。以下では、目的別に最適な順番を解説します。
パフォーマンス向上に効く順序の真実
<筋トレ → ランニングが効果的なケース>
- フォーム安定や姿勢強化が目的
- 筋力の向上がテーマ
- 大会までまだ時間がある場合(オフシーズン~ビルド期)
この順番のメリットは、筋トレ後に疲労した状態で走ることで「ランニング中の筋持久力」を鍛える“耐乳酸トレーニング”になります。レース終盤の粘りに効果的です。
<ランニング → 筋トレが効果的なケース>
- スピードや走力向上を優先したい
- 疲労を残したくない
- 大会が近いピーク期(テーパリング中など)
先にランニングを行うことで、走行フォームに集中でき、怪我のリスクも下がります。筋トレは補助的に取り入れる形で、体幹や可動域の維持を目的とします。
「走力を優先したいならラン→筋トレ、筋力をつけたいなら筋トレ→ラン」が基本方針です。
また、筋トレとランの間に最低でも30分のインターバルを入れると、相互干渉を抑えられるとする研究結果もあります(特に筋タンパク合成の観点から)。
目的別(脂肪燃焼・持久力アップ・筋力維持)での使い分け
|
目的 |
最適な順番 |
トレーニング内容例 |
|
脂肪燃焼 |
筋トレ → 有酸素運動 |
スクワット→ラン30分 |
|
持久力向上 |
ラン → 筋トレ |
ジョグ60分→体幹ドリル |
|
筋力維持 |
筋トレ単独(後日ラン) |
重量トレーニングのみの日を設定 |
|
怪我予防 |
ラン → ストレッチ&補強 |
ジョグ→ヒップリフト、プランクなど |
|
大会前調整 |
軽めラン+体幹 |
低強度ジョグ+フォーム意識系 |
順番の判断に迷った場合は「疲労を残したくない方を先に行う」ことが原則です。大事なポイント練習がある日は、筋トレは翌日に回す方が安全です。
マラソン期には、筋トレの“質よりバランス”が勝負の鍵を握ります。

北野 優旗
筋トレとランニングを同日にやると、どうしてもどちらかが疎かになりがちです。可能であれば「朝に走る・夜に筋トレ」「曜日で分ける」など、身体に無理をさせない“分割戦略”を意識してみてください。
なぜマラソンランナーに筋トレが必要なのか?
の本文を作成いたします。
「長距離を走るなら、筋肉よりスタミナが大事じゃないの?」と思われがちですが、近年の研究では“筋トレの有無”がマラソン成績に大きく影響することが明らかになっています。持久力や心肺機能と同じくらい、「筋肉の耐久性と出力」が、フォームの維持・怪我予防・レース終盤の粘りに不可欠です。
マラソンで求められるのは“筋持久力”であり、筋肉の土台がなければ記録も身体もすぐに限界に達します。
特に筋トレが効果的なのは、以下の3つの要素に関してです。
長距離だけでは鍛えられない部位とは
長距離走によって鍛えられるのは主に「心肺機能」と「有酸素的筋繊維(遅筋)」ですが、フォームを維持するための「速筋」や「補助筋群」はあまり刺激されません。結果、以下のような問題が発生します。
- 骨盤や体幹が落ちることでフォームが崩れる
- 着地の衝撃に耐えきれず膝や足首に痛みが出る
- 後半になると体がブレてスピードが失速する
筋トレによって、これらを支える「臀筋」「脊柱起立筋」「腸腰筋」などが強化され、“走りを支える筋肉”の耐久性がアップします。
筋トレが走りを変える!科学的に裏付けられた理由
筋トレがマラソンに有効であることは、国内外の複数の研究で証明されています。
- VO2Max(最大酸素摂取量)に加えて、ランニングエコノミーが改善
- 長時間の運動でもフォームが維持されやすくなる
- 筋損傷や遅発性筋肉痛(DOMS)の軽減
特に「ランニングエコノミー」の向上は注目ポイントで、“同じスピードで走っても疲れにくくなる”という実用的なメリットがあります。
「筋肉は重くなる」は本当か?マラソン神話を検証
「筋トレをすると脚が重くなって走れなくなる」と言われることがありますが、これは誤解です。正しく筋トレを行えば、むしろ筋肉の「収縮効率」や「持久力」が高まり、体重増加よりも“パフォーマンスの上昇”がはるかに上回るという研究結果もあります。
また、マラソンで求められる筋肉は「大きさ」よりも「質と持続力」です。ボディビルダーのように筋肥大を目指すのではなく、自重や中負荷で回数を重ねる「筋持久力特化型のトレーニング」が鍵です。
筋トレは“速くなるための補助輪”ではなく“必要不可欠な車輪”です。

北野 優旗
「筋トレ=筋肥大」ではありません。マラソンに必要なのは“軽くて強い筋肉”。そのためには、自分の体重を使ったトレーニングや体幹メニューを中心に、1回1回を丁寧に効かせるトレーニングがベストです。
実例で学ぶ!マラソンランナーたちの筋トレ習慣
の本文を作成していきます。
筋トレの重要性はわかっても、「実際にどんな人がどのように筋トレを取り入れているのか?」を知りたいランナーは多いでしょう。そこでここでは、市民ランナーからトップアスリートまでの筋トレ習慣を紹介しながら、あなた自身のトレーニング計画のヒントになるような実例を解説します。
筋トレは「やってみて実感できる変化」が大きいトレーニングです。
習慣化された筋トレは、単にパフォーマンスを上げるだけでなく、トレーニングへの自信やメンタルの安定にも大きく貢献しています。
市民ランナーの成功例:筋トレ導入後のタイム変化
ある40代男性ランナー(サブ4.5クラス)は、フルマラソン中盤以降の足攣りとフォーム崩れに悩んでいました。週に1~2回の自重トレ(スクワット・プランク・ブルガリアンスクワットなど)を3ヶ月継続した結果、後半のラップタイムが大幅に安定し、自己ベストを30分更新。
また、30代女性ランナー(サブ3.5)は、体幹トレを中心に取り入れたことで、呼吸が安定し、心拍数の上昇を抑えられたことを実感。筋肉量はほとんど変わらなかったものの、「走りが軽くなった」というフィードバックも。
主な変化点(複数ランナー共通):
- フォームのブレが減り、後半も安定
- 怪我や筋肉痛の頻度が大幅に減少
- 長距離でも集中力が持続するように
- シューズやフォームの選択に自信が持てるようになった
筋トレの効果はタイムだけでなく、“走ること自体が楽になる”という実感に現れます。
トップアスリートの筋トレメニューに学ぶ
箱根駅伝出場校の多くでは、ランナー専用の筋トレメニューをチーム全体で実施しています。特に共通して重視されているのは、「体幹強化」と「股関節可動域の維持」。この2つをトレーニングルーチンに取り入れることで、フォームの維持率が飛躍的に向上するといわれています。
日本代表クラスの長距離選手も、週に2~3回の体幹・補強トレを欠かしません。彼らは「走り込み期」「調整期」で筋トレメニューを細かく変えており、以下のような分類が一般的です。
- 走り込み期:スクワット、ランジ、ヒップリフト、体幹静止系(負荷高め)
- スピード強化期:体幹ダイナミック系、ジャンプトレ、バランス系
- 大会直前期:股関節ドリル、ストレッチ、可動域確保中心(負荷軽め)
これらを見てわかる通り、強くなるランナーほど、筋トレを“戦略的に”活用しているのです。
年齢・性別別で変わる筋トレの最適化
筋トレは「万人に同じメニュー」で良いわけではありません。年齢や性別によって、最適な強度・頻度は変化します。
- 40代以上のランナー:関節への負担が増えるため、自重トレと可動域強化が中心。無理な高負荷はNG。
- 女性ランナー:筋力不足を補うだけでなく、骨密度向上のためにも適度な筋トレが重要。内転筋・腸腰筋を重点的に。
- 20~30代の男性ランナー:筋トレとスピード練習の両立が可能な時期。下半身・体幹・姿勢保持に力を入れると良い。
「年齢=衰え」ではなく、「年齢に合わせたトレーニング設計」が強くなる鍵です。

北野 優旗
「筋トレでタイムが縮まるなんて信じられなかった」という声を多く聞きます。でも、実際に始めてみると、3ヶ月後には走りが明らかに変わってきます。小さな積み重ねが、レース後半の大きな差になりますよ。
避けたいNG筋トレ:マラソンパフォーマンスを下げる落とし穴
の本文を作成していきます。
筋トレはマラソンに有効なトレーニングですが、やり方を間違えると、むしろ走力の低下や怪我のリスクが高まる可能性もあります。SNSやYouTubeで紹介されているトレーニングを“見よう見まね”で取り入れる前に、マラソンに合った適切な方法を知っておくことが重要です。
筋トレは「やり方」より「合っているかどうか」で効果が決まる。
ランナーが気をつけたいNGポイントを事前に把握しておくことで、効率よく、安全に筋トレ効果を得ることができます。
筋肉をつけすぎてスピードダウン?その真相とは
「筋肉をつけすぎると脚が重くなってペースが落ちる」という不安は、実はあながち間違いではありません。ただし、それは“筋肥大目的の高負荷トレーニング”を誤って取り入れた場合です。
- 高重量×低回数(3~6回)×多セット:筋肥大・パワー向け(マラソン非推奨)
- 中重量×中回数(10~15回)×少セット:筋持久力向け(マラソン推奨)
- 自重やチューブを使った反復系:フォーム・可動域強化向け(初心者向き)
特に筋肥大を狙ったベンチプレスやデッドリフトなどは、マラソンに必要のない筋群(上腕三頭筋・広背筋)を過度に鍛えてしまうことも。必要以上に筋肉量を増やすと、心拍数やエネルギー消費が増えるため、持久走ではマイナスになる可能性もあります。
マラソンランナーに必要なのは“軽くて長持ちする筋肉”です。
回復を無視したスケジュールがもたらす代償
マラソンランナーにとって、トレーニングと同じくらい大切なのが「休養」です。筋トレのやりすぎや、ランと連日の併用で疲労が蓄積すると、以下のようなリスクが急増します。
- 慢性疲労症候群(パフォーマンスが低下したまま戻らない)
- 睡眠の質の低下
- 筋肉痛や関節痛が常時ある状態
- ランニングの質が落ち、タイムも伸びない
週に1~2日は「完全休養日」を設けることで、筋肉の超回復や神経系のリセットが可能となります。
また、筋トレとランを同日に行う場合は、どちらかを「低強度」に調整するのが鉄則。両方ハードにしてしまうと、身体がオーバートレーニング状態になり、回復が追いつかなくなります。
「やらない日」があるからこそ、「やる日」が生きてくるのです。
間違ったフォームが生む怪我リスクとその対策
筋トレで多いミスは、「効果が出ない」ではなく「フォームの崩れからくる怪我」です。特に多いのが、スクワットでの膝の向きや、プランクでの腰の反りなど。これらを放置すると、以下のような症状が出ることがあります。
- 膝の痛み(ランナー膝/腸脛靭帯炎)
- 腰痛(反り腰/腹筋不足)
- 足首や股関節の違和感(可動域の制限)
対策としては、最初は鏡やスマホでフォームを録画して確認したり、ジムでトレーナーに1回だけでも見てもらうことをおすすめします。また、自重トレを徹底してからダンベルなどを取り入れる流れが理想です。
正しいフォームは、効果と安全を両立する“最強の武器”です。

北野 優旗
筋トレをがんばっているのに走力が落ちているなら、まずは「回復不足」と「フォームの確認」を疑ってください。筋トレの効果はすぐには出ませんが、1~2ヶ月後に「明らかに違う」と感じられるはず。焦らず、丁寧に。
参考論文:Overtraining syndrome: a practical guide(オーバートレーニング症候群:実践ガイド)
マラソンに筋トレを活かす食事とサプリメント
の本文を作成していきます。
筋トレとランニングの効果を最大化するためには、「食事」と「サプリメント」の戦略が不可欠です。いくら正しい筋トレを行っても、栄養が不足していれば筋肉は回復せず、逆に怪我や疲労の原因にもなりかねません。
「トレーニング×栄養補給」のセットで初めて、走力と筋力がバランスよく伸びるのです。
ランナーは「太らないようにカロリーを抑えたい」という傾向がありますが、筋肉を維持・強化するには最低限の栄養が必要です。特に、筋トレとランニングを併用する場合は、エネルギー消費が大きくなるため、食事でのリカバリーを戦略的に考えなければなりません。
筋肥大じゃない、筋持久力を高める栄養戦略
マラソンに必要なのはボディビル的な筋肥大ではなく、「筋肉の耐久性と収縮力」です。これを実現するには、以下のような栄養設計が効果的です。
- タンパク質(Protein) → 筋合成・回復の鍵。1日あたり体重1.2~1.5gが目安
- 炭水化物(Carbohydrate) → エネルギー源。筋トレ+ランでは1日5~7g/kgを確保
- 脂質(Fat) → ホルモンバランスを保ち、炎症を抑える役割も。全体の20~30%以内を目安に
- ビタミン・ミネラル類 → マグネシウム、鉄、亜鉛、ビタミンB群などは特に重要。汗で失いやすいため意識的に補給が必要
「タンパク質+炭水化物のタイミング補給」が筋肉の回復と成長に直結します。
トレーニング後30分以内の「ゴールデンタイム」に、プロテインやバナナ、エネルギーバーなどを摂取すると、筋分解を防ぎ、回復が促進されます。
プロテイン、BCAA、クレアチン…何を摂るべき?
ランナーにとって「サプリメント」はあくまで“補助的な選択肢”ですが、忙しい現代人にとっては非常に有効な武器となります。
|
サプリメント名 |
主な効果 |
推奨摂取タイミング |
注意点 |
|
ホエイプロテイン |
筋合成促進・回復 |
トレーニング直後 |
乳製品アレルギーがある人は要注意 |
|
BCAA(分岐鎖アミノ酸) |
筋分解の抑制・疲労軽減 |
トレ中~直後 |
1回5g前後が一般的 |
|
クレアチン |
筋力向上・瞬発力UP |
トレ前または毎日摂取 |
体重が増える可能性あり |
|
マルチビタミン |
代謝サポート・免疫維持 |
食後 |
過剰摂取に注意 |
|
グルタミン |
免疫サポート・疲労回復 |
トレ後・就寝前 |
高強度の週におすすめ |
BCAAやプロテインは、トレーニングを習慣化している人にとって非常に効果が実感しやすく、「筋肉痛の軽減」や「翌日の疲労感の減少」などが体感されやすいポイントです。
走る日・筋トレ日で食べ方を変える理由
走る日と筋トレ日では、エネルギーの消費構造が異なります。そのため、以下のような「目的に応じた栄養の最適化」が有効です。
- 筋トレ日:タンパク質多め(1.5g/kg)、脂質はやや控えめ、炭水化物は中程度
- 長距離走の日:炭水化物多め(7g/kg前後)、タンパク質も適度に、塩分や水分も意識
- 完全休養日:全体的に少なめに調整。抗酸化食材(トマト・緑茶・ベリー類など)を積極的に
食事も「走るための準備と回復の一部」として捉えることが、パフォーマンスの安定につながります。

北野 優旗
「サプリは怖い」「何を選べばいいか分からない」と言う方は、まずはホエイプロテインから始めてみましょう。人工甘味料なしのナチュラルタイプを選ぶと、胃にも優しく続けやすいですよ。
参考論文:Nutritional strategies to support concurrent training(同時トレーニングをサポートする栄養戦略)
Q&A:よくある質問
の本文を作成していきます。
ここでは、「マラソン×筋トレ」に関して多く寄せられる疑問に対して、トレーナー目線でわかりやすくお答えします。初めて筋トレを取り入れる方や、実践中のランナーの悩みにフォーカスしているので、自分に当てはまる項目があるかぜひチェックしてみてください。
筋トレすると脚が太くなるって本当?
答え:いいえ、基本的には太くなりません。
マラソンランナーが取り入れる筋トレは「筋持久力向上」が目的であり、ボディビルのような筋肥大トレーニングとは異なります。特に自重や中負荷・高回数のトレーニングでは、筋肉の密度や神経伝達能力が向上し、見た目は引き締まる傾向にあります。
むしろ、適度な筋トレは「細くてしなやかな筋肉」を作ることに貢献します。
ランニングと筋トレ、同じ日にやってもいいの?
答え:目的と体調に応じてOK。順番が重要です。
筋トレとランニングを同日に行う場合は、「走力アップ」が目的ならラン→筋トレ、「筋力アップ」が目的なら筋トレ→ランの順がおすすめ。また、どちらかを“軽め”に抑えることで疲労の蓄積を防げます。
インターバルを30分以上空ける、朝と夜に分けるなどの工夫も有効です。
女性ランナーも筋トレすべき?
答え:もちろんYESです!むしろ積極的に推奨されます。
女性は男性に比べて筋力が少なく、関節が柔らかいため、筋肉のサポートが非常に重要です。 特に腸腰筋・内転筋・体幹周りを鍛えることで、怪我予防や姿勢改善、走行安定性の向上が期待できます。
また、筋トレによる基礎代謝向上も、女性ランナーのダイエットや体型維持に役立ちます。
ジムに通う必要はある?自宅トレでも十分?
答え:自宅トレでも十分に効果があります。
スクワット、ランジ、プランク、ヒップリフトなど、効果的な筋トレはすべて自重で可能です。 ジム器具を使えば負荷の調整がしやすくなりますが、正しいフォームと継続があれば、自宅でもしっかり成果は出ます。
おすすめは、「まず自宅で習慣化 → 物足りなくなったらジムへ」です。
ダイエット目的でも筋トレは必要?
答え:むしろ筋トレは必須です。
筋トレは筋肉量の維持・増加により「基礎代謝が上がる」ため、ダイエット効果を大きくサポートします。また、筋肉が減るとエネルギー消費が落ちてしまい、痩せにくい体質になるリスクもあります。
ランと筋トレを並行することで、「脂肪は落とし、筋肉は残す」という理想的なボディバランスが実現します。
筋肉痛の時でも走っていいの?
答え:軽い筋肉痛ならOKですが、強い痛みがある場合はNGです。
筋肉痛は「筋繊維の微細損傷」による反応です。軽度であればウォーキングや軽いジョグで血流を促し、回復を助けることができますが、強い痛みや関節に違和感がある場合は休養が最優先です。
「走る=偉い」ではなく、「回復できる=強くなる」と考えて行動しましょう。
まとめ
の本文(1500文字以上)を作成いたします。
筋トレとマラソン――この2つの関係性は、かつては相容れないものと考えられてきました。しかし、現代のスポーツ科学と実際のトレーニング現場では、「筋トレこそが走力向上の裏エース」であることが明らかになっています。筋肉は単なる“スピードのブレーキ”ではなく、“推進力と安定性の源”です。
本記事では、マラソンランナーにとっての筋トレの重要性、実際に効果のある種目、スケジューリングのコツ、さらには栄養戦略やNG行動まで、あらゆる角度から詳しく解説してきました。
初心者ランナーの方には、「まず体幹と下半身を中心に、自重トレーニングから始めること」をおすすめします。たった10分のトレーニングでも、フォームや疲労感に大きな変化を実感できるはずです。
中級~上級者にとっては、スピードアップやレース後半の粘り、そして怪我をしない身体作りが課題となります。そのどれもを支えてくれるのが、筋トレなのです。
また、筋トレの成果を最大限に引き出すためには、栄養補給や休養の取り方もセットで考えることが必要不可欠です。どんなに良いトレーニングをしても、睡眠やタンパク質が不足していれば回復は進まず、逆にパフォーマンスが落ちてしまうこともあります。
筋トレとランの併用は難しそうに思えるかもしれませんが、コツさえつかめばむしろシンプルです。
最後に、今日から実践できる3ステップをまとめます。
- 週に2回の自重筋トレからスタートする → スクワット、ランジ、プランクでOK。回数より“継続”を大事に。
- 走る日と筋トレ日を分けて、回復もトレーニングと考える → 完全休養日を設けて、トレーニング効率を高めましょう。
- プロテイン+炭水化物のタイミング補給を習慣化する → トレ後30分以内の補給で、筋肉は確実に応えてくれます。
これらを実践すれば、あなたの走りは確実に変わります。タイムが伸び悩んでいた人は記録が更新され、怪我に悩んでいた人は「走るのが楽しくなる」体に出会えるでしょう。
筋トレは、マラソンにとって“足し算”ではなく“掛け算”です。
「走るだけでは物足りない」「もっと強くなりたい」「自分の限界を突破したい」――そう感じているすべてのランナーに、筋トレという武器を手にしてもらいたい。それが、この記事の一番の願いです。
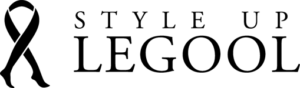



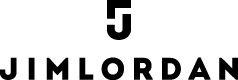





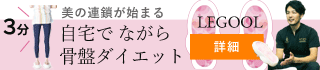
コメント