筋トレの中でも王道とされる「スクワット」。そのトレーニング効果を数値で把握できる「スクワット換算」は、自己管理にもトレーニング計画にも役立つ重要な指標です。しかし、換算表の仕組みや正しい使い方を知らないままでは、本来の成果を見誤ることも。この記事では、スクワット換算の基本から応用までを、科学的根拠とともに徹底的に解説していきます。
こんな人におすすめの記事:
- 1RMの意味や計算方法がわからない初心者
- スクワットの成果を数値で知りたい人
- 換算表を使ったトレーニング設計をしたい人
- RMの仕組みに疑問がある中上級者
- 科学的な裏付けで自分の実力を分析したい人
目次
スクワット換算とは?まずは“1RM”を正しく理解しよう
スクワット換算とは、1回しかできない最大重量(1RM=ワンレップマックス)を基準として、自分のトレーニング負荷を数値で管理する方法です。例えば「100kgを10回上げられる人の1RMは約133kg」といったように、回数と重量から最大筋力を予測するもの。この仕組みを理解することで、自分の筋力の成長度を定量的に把握できるようになります。
そもそも1RM(ワンレップマックス)って何?
1RM(ワンレップマックス)とは、1回だけ挙上できる最大重量を意味します。筋力の指標として世界的に使われており、競技者だけでなくフィットネス愛好者にとっても重要な指標です。1RMは筋力だけでなく、筋持久力や神経系の発達具合も反映するため、正確に把握することはトレーニングの質を大きく左右します。
たとえば、ベンチプレスで60kgを10回持ち上げた場合、それを元に換算すると1RMは約80kg。RM換算は「重量 × 回数 ÷ 33.3 + 重量」やEpley式、Brzycki式など複数の公式がありますが、どれも共通して「高回数での挙上重量」から「理論上の最大筋力」を導く仕組みです。
重要なのは、実際に1RMを試すよりも、安全かつ正確に“予測”できるという点。これにより、ケガのリスクを減らしながら筋力レベルを把握することが可能になります。
さらに、筋トレの進捗管理や記録にも使いやすく、アスリートやボディメイクを目指す人はもちろん、ダイエットや健康維持の一環としてトレーニングをする人にとっても有用です。
「RM換算」で何がわかる?筋力を見える化するロジック
RM換算とは「Repetition Maximum(最大反復回数)」を使って、自分の筋力を客観的に把握する手法です。たとえば「80kgを5回上げられる」という情報だけでは他者と比較できませんが、それをRM換算することで「あなたの1RMは約93kg」と言えるようになります。
RM換算にはいくつかの公式があります。以下に代表的な計算式を紹介します。
|
式の名称 |
計算式 |
特徴 |
|
Epley式 |
重量 × 回数 ÷ 30 + 重量 |
最も使われる一般的な式 |
|
Brzycki式 |
重量 ÷ (1.0278 – 0.0278 × 回数) |
回数が多いとやや精度が落ちる |
|
Lombardi式 |
重量 × 回数^0.10 |
高回数に強い傾向 |
これらを使うことで、自分の強度に合ったトレーニング設計がしやすくなります。特にEpley式は簡便でありながら精度も高く、多くのアスリートに使われています。

北野 優旗
「RM換算は“目安”と心得ることが大切です。実際の1RM測定とは異なり、身体コンディションやフォーム次第でズレが出るため、無理な負荷設定は避けましょう。」
スクワットにおける換算の意義:自重派にも恩恵あり
スクワットのRM換算は、バーベルを使わない“自重トレーニング派”にも大きなメリットがあります。自重でも回数や動作速度、可動域を意識すれば、筋力の推移をある程度数値で追うことが可能です。
たとえば、通常の自重スクワットで「30回が限界だったのが、数週間後には50回できるようになった」なら、それは相対的に筋持久力が向上し、間接的に筋力アップしている証拠。この変化を数字で表すには、1RM換算はとても便利です。
もちろん、自重スクワットの「1RMを正確に出す」ことは難しいですが、以下のような視点から活用できます。
- 反復回数の増加→負荷が足りないサイン
- 片足スクワットへの移行→換算負荷を高める手法
- 動作スピードを遅く→時間当たりの張力を増やす工夫
つまり、RM換算の考え方はバーベル使用者だけでなく、トレーニング強度の“判断軸”としてあらゆるレベルの人に使えるのです。
特に初心者は「重さがないから成長を実感しにくい」と感じがちですが、回数と換算の視点を取り入れることで、成長の可視化が可能になります。

北野 優旗
「自重でもスクワット換算の概念は使えます。数字で見える化することで、成長を“体感”ではなく“確認”できるようになるのが強みです。継続のモチベーションにもつながります。」
初心者でも安心!スクワット換算の仕組みと基本式をマスター
筋トレ初心者にとって、スクワットの換算式や数値は「なんだか難しそう」と感じるかもしれません。ですが、基本となる計算式さえ押さえれば、誰でも簡単に自分の筋力を“見える化”できます。1RM(ワンレップマックス)を求めることは、単に自分の限界重量を知るだけではなく、安全に効率的なトレーニング計画を立てるためにも必要なプロセスなのです。
換算式は複数ありますが、初心者でも使いやすいのが「Epley式」。この式は、現在扱っている重量と回数から理論的な最大挙上重量を導き出すことができます。次のセクションではその式の詳細と使い方を見ていきましょう。
箇条書き:RM換算式の基本を学ぼう
- Epley式:重量 × 回数 ÷ 30 + 重量(例:80kg×10回→約106.7kgが1RM)
- Brzycki式:重量 ÷(1.0278 – 0.0278 × 回数)(例:80kg×10回→約106kg)
- Lombardi式:重量 × 回数^0.10(例:80kg×10回→約107kg)
初心者はEpley式が最もシンプルかつ実用的でおすすめです。
回数と重量の関係性:換算式「重量 × 回数 ÷ 33.3 + 重量」とは
この式は、最も簡単に1RM(最大挙上重量)を算出するための目安として用いられる代表的な換算式です。具体的には「重量 × 回数 ÷ 33.3 + 重量」という形で、例えば100kgを10回持ち上げたとすると、100×10÷33.3+100=130kgとなり、理論上の1RMが算出されます。
なぜ「33.3」で割るのかといえば、これは経験則に基づく値であり、10回の反復が1RMの約75%に相当するというトレーニング理論から導き出された数字です。この式は手軽に計算できるうえに、多くのジムでも使われている一般的な方法です。
この換算式を使うことで、実際に限界重量を試すことなく、自分の最大筋力を“安全かつ精度高く予測”することができます。
この式の魅力は、「回数と重量さえわかればすぐに算出できる」という点です。特に初心者がいきなり1RMに挑戦するのは危険なので、RM換算式はとても重要な安全対策とも言えるでしょう。

北野 優旗
「フォームが安定していないうちは、実測の1RMテストより換算式を活用したほうがケガを防げます。正確なフォームと感覚を身につけてから、段階的に強度を上げていきましょう。」
RM換算表の見方:数値に惑わされない正しい使い方
RM換算表は便利なツールですが、正しく読み取らなければ効果が半減します。この表は「挙上できる回数」と「その重量」に基づいて、おおよその1RMを導き出す早見表として利用されます。例えば「90kgを5回上げられる人は、およそ105~110kgの1RMがある」といった具合です。
RM換算表を使う上でのポイントは、あくまで「目安」であり、個々の筋力特性やフォーム、体調によって結果が前後することです。以下に典型的なRM換算表の一例を示します。
|
回数 |
換算係数 |
100kgでの1RM相当 |
|
1 |
1.00 |
100kg |
|
2 |
1.047 |
104.7kg |
|
3 |
1.093 |
109.3kg |
|
5 |
1.160 |
116kg |
|
8 |
1.233 |
123.3kg |
|
10 |
1.300 |
130kg |
|
12 |
1.347 |
134.7kg |
この表の使い方は非常に簡単で、「実際に上げた重量 × 換算係数」で概算の1RMがわかります。しかし注意すべき点もあります。
- フォームの乱れがあると正しい換算にならない
- 自分が“ギリギリ”で上げた回数で判断する
- 疲労や精神状態によっても変動が大きい
RM換算表は、“正しいフォームでの限界回数”を基に使うことで最大の効果を発揮します。たとえば「90kgを5回、楽に上げられる」なら実際の1RMは表より高い可能性もありますし、「ギリギリ10回」なら表通りが妥当です。
また、換算係数は個人差があります。筋持久力型の人と爆発的筋力型の人では、同じ回数でも換算される1RMが大きく異なる場合があります。そのため、1つの表に頼りすぎるのではなく、目安として複数の計算方式や自身の記録と照らし合わせて使うのがベストです。

北野 優旗
「換算表は初心者にとって非常に便利なツールですが、盲目的に信じるのではなく“参考値”として活用しましょう。正しいフォームでの反復数が最も信頼性のあるデータです。」
デッドリフト・ベンチとの違いも比較しよう
スクワットのRM換算は、他のビッグ3種目である「デッドリフト」「ベンチプレス」と比較して、フォームや関与する筋群の特性により精度や活用の仕方に差があります。このため、それぞれの種目でRMを求める際には異なる注意点を押さえる必要があります。
まず、以下の比較表をご覧ください。
|
種目 |
主に使う筋肉 |
RM換算のしやすさ |
傾向 |
|
スクワット |
大腿四頭筋・ハムストリング・臀筋等 |
◎ |
安定性が高く予測しやすい |
|
ベンチプレス |
大胸筋・三角筋・上腕三頭筋 |
◯ |
上半身種目のため個人差大 |
|
デッドリフト |
脊柱起立筋・ハムストリング・広背筋 |
△ |
フォームや神経依存が強い |
このように、スクワットは下半身の大筋群を使うため、他の種目に比べて回数と重量の相関が比較的安定しており、RM換算がしやすいのが特徴です。
一方、ベンチプレスは個人の肩関節の可動域や神経系の発達により回数耐性が変わるため、「10回で130kgいける」といった単純な換算がスクワットほど信頼できない場合もあります。また、デッドリフトは最も換算が難しい種目とも言われ、日によってフォームや疲労の影響を受けやすく、1RM換算との誤差が生じやすいのが現実です。
さらに、スクワットは可動域やフォームの安定性が比較的高いため、トレーニング歴が短い人でも正確な換算値が出やすいという利点もあります。これに対して、ベンチプレスやデッドリフトは「怪我のリスク」「フォームの崩れ」が成否を大きく左右するため、RM換算に頼りすぎるのは危険といえるでしょう。
要するに、スクワットはRM換算において最も信頼しやすい種目であり、トレーニング設計にも積極的に活用できます。

北野 優旗
「スクワットはRM換算との相性が抜群です。ただし、ベンチやデッドリフトで同様に使う場合は、可動域や神経支配の個人差を考慮して“やや低め”の予測で使うと失敗を避けられます。」
スクワット1RM換算を実際にやってみよう
これまでRM換算の理論や式について学んできましたが、ここからは実際に数字を用いて「どうやって1RMを算出するのか?」を体験的に理解していきましょう。自分のトレーニング記録をもとに計算すれば、RM換算は決して難しくなく、むしろトレーニングの質を高める非常に便利な武器になります。
特に「1回の限界に挑むのが怖い」「まだ筋力に自信がない」という方でも、過去の記録を使えば理論的に自分の筋力がどれほどかを把握できます。ここでは換算例とツール活用法を通じて、その実践的な方法を紹介します。
テーブル:1RM換算の実例と計算比較(Epley式使用)
|
実施重量 |
挙上回数 |
換算結果(1RM) |
|
100kg |
10回 |
133kg |
|
90kg |
8回 |
119.2kg |
|
80kg |
12回 |
111.8kg |
|
120kg |
3回 |
132kg |
数字を出すことで“感覚”が“確信”に変わり、自信と計画性が生まれます。
100kgを10回=130kg?換算事例で感覚を掴む
最もわかりやすいRM換算例として、100kgを10回上げたケースを取り上げましょう。 Epley式に当てはめると以下の通りです。
1RM = 重量 × 回数 ÷ 30 + 重量 → 100 × 10 ÷ 30 + 100 = 33.3 + 100 = 133.3kg
このように、「自分では100kgまでしか扱っていない」という人でも、実際には130kg以上の筋力がある可能性が見えてくるのです。これを知ることで、たとえば次回のメニューを「1RMの80%で設定しよう」と具体的にプランニングすることができます。
さらにこの理論を応用すれば、筋力向上の“見える化”が可能になります。以下のような変化が、トレーニング効果の証明となるのです。
- 同じ重量で回数が増える → 1RMが上がっている
- 同じ回数で重量が上がる → 1RMが上がっている
- 1RMが上がった → 筋力が強化されている証拠
RM換算は、毎回のトレーニングの「見えない成果」を数値化する最高の武器になります。
また、過去のトレーニング記録を表形式で残しておけば、自分の成長がグラフで視覚的に確認できるため、モチベーションの向上にもつながります。

北野 優旗
「最初はざっくりでOKです。フォームが安定しているときに記録をとって、無理のない回数(6~10回程度)でRM換算すれば、安全かつ効果的に筋力管理ができます。」
スマホで簡単!おすすめの1RM計算ツール3選
1RMを手軽に知りたいなら、スマホやPCで使える無料ツールを活用するのが断然おすすめです。最近では、入力するだけで自動計算してくれるウェブアプリやフィットネスアプリも数多く登場しています。
ここでは使いやすさと信頼性を重視して厳選した、1RM計算ツールを3つ紹介します。
箇条書き:おすすめ1RM計算ツール
- 筋トレ計算機(smartlog.jp) シンプルなUIで「重量」と「回数」を入れるだけ。Epley式ベースで計算してくれる。
- keisan.casio.jpの1RM計算機 計算精度に定評あり。複数の換算式に対応しているのが強み。
- Strength Level(strengthlevel.com) 海外サイトだが種目ごとに筋力レベル比較までできる。日本語非対応でも直感的に使える。
使い方はどれも非常に簡単で、たとえば「80kgを8回」と入力するだけで、1RMだけでなく、75%・85%などのゾーン別重量まで表示してくれるものもあります。
これらのツールを活用することで、手間をかけずに自分の筋力データを把握し、トレーニング設計に反映することができます。
さらに、スマホのホーム画面にブックマークしておけば、ジムでのリアルタイム確認も可能です。思いついたときにすぐ確認できることで、「今日は何キロで何回やるべきか?」を判断するのにも役立ちます。

北野 優旗
「紙に書くより、今はアプリ時代。自動計算に任せて、あなたはフォームや集中力に意識を向けましょう。」
スクワット換算表でわかる自分の筋力レベル
1RMを算出できるようになったら、次はその数値が「どの程度の筋力レベルに相当するのか?」を知りたくなりますよね。スクワットの換算値は、あなたの筋力が「初心者レベル」なのか「中級者」あるいは「アスリートレベル」なのかを判断するための強力な指標になります。
体重との比率で評価する方法が一般的で、「自体重×1.5倍をスクワットできれば中級者」といった基準があります。次のセクションでは、国際的な目安と照らし合わせながら、自分の位置を確認していきましょう。
テーブル:体重別の筋力レベル判定(男性向けの一例)
|
体重(kg) |
初心者(×1.0) |
中級者(×1.5) |
上級者(×2.0) |
|
60 |
60kg |
90kg |
120kg |
|
70 |
70kg |
105kg |
140kg |
|
80 |
80kg |
120kg |
160kg |
|
90 |
90kg |
135kg |
180kg |
女性の場合は、これらの数値を70~75%にスライドして考えると適切です。
あなたの換算1RMが体重の1.5倍以上なら、中級者と名乗ってOKです。
体重×1.5倍で中級?国際基準と照らし合わせてチェック
スクワットの筋力レベルを測るとき、多くのトレーナーが「体重比」を指標にします。この方法は、個々の体格差を考慮できるため、性別・年齢・体型に関係なくフェアに筋力を評価できます。
たとえば体重70kgの男性が105kgを1RMでスクワットできるとしたら、105 ÷ 70 = 1.5倍となり「中級者レベル」と判断できます。逆に、70kgで80kgしかできない場合は、1.14倍となりまだ初級者の域。目標が明確になれば、日々のトレーニングにも張りが出ます。
また、StrengthLevel.comのようなサイトでは、年齢や体重、性別ごとの詳細なレベル指標(Novice, Intermediate, Advanced, Elite)が掲載されています。そこでは、スクワット1RMが体重の2倍に達すると「上級者レベル」とされることが多いです。
ただし、ここで重要なのは「高ければ高いほど偉い」という考えではなく、自分の目標と現在地を把握することです。
- 自体重×1.2倍 → 初級者からの卒業ライン
- 自体重×1.5倍 → 中級者の目安
- 自体重×2.0倍 → 上級者 or アスリートレベル
この基準は、筋肉量だけでなくフォーム、安定性、神経系の発達も含めた“全体力”の証明です。
つまり、換算1RMはただの数値ではなく、あなたのトレーニングの信頼性や努力の証しと言えるのです。

北野 優旗
「体重比で判断する方法はモチベーション維持に効果的です。数値を意識することで、明確な“目標”と“進捗”が得られます。数字はあなたの味方になります。」
ズレる理由は?フォーム・日による差・個体差も考慮せよ
RM換算はあくまで「理論値」であり、現実には誤差やズレが起きるのが普通です。たとえば、「10回できたら130kgが1RMのはずなのに、実際には120kgが限界だった…」というような違和感を感じたことがある人は少なくありません。このズレには明確な理由があります。主な要因は以下の通りです。
箇条書き:RM換算がズレる5つの原因
- フォームの違い:可動域の浅さや姿勢の乱れが重量に影響
- その日の体調や疲労度:睡眠不足や栄養状態も1RMに影響
- 神経系の影響:神経発火効率が日によって変わる
- 回数耐性の個人差:筋持久力型か瞬発力型かでズレが生じる
- ウォームアップの質:筋肉の活性化不足で本来の力が出せない
つまり、RM換算は「その日の自分の実力の平均値」ではなく、「理論的にこれくらいできるだろう」という目安に過ぎません。
特にフォームの違いは非常に重要です。たとえば、スクワットで深くしゃがむ「フルスクワット」と、太ももが床と平行になる程度の「パラレルスクワット」では、同じ重量でも負荷のかかる筋肉や神経系の刺激が異なるため、1RM換算にズレが生じます。
また、筋肉の疲労が蓄積していたり、前日に他の種目を多く行った日には、普段より重量が持てなくなることがあります。これは一時的なものであり、「自分の筋力が落ちた」と勘違いしないことが大切です。
そして、RM換算が正確でないケースは、初心者よりも中~上級者に多く見られます。なぜなら、強くなればなるほどフォームや神経系の細部が結果に大きく影響を与えるためです。
RM換算は万能ではなく、ズレを許容した上で使うことが重要です。

北野 優旗
「ズレは誰にでも起こります。むしろ“ズレがあるからこそ、自分の体と対話する姿勢”が大事です。過信も軽視もしない。これが賢いRM換算の使い方です。」
「なぜか計算より重い(or軽い)」現象への考察
RM換算をしてみたら「なんでこんなにズレてるの?」と感じたことはありませんか?たとえば「計算では1RMが130kgなのに、120kgすら挙がらなかった」「逆に、150kgが意外と挙がった」などの現象は、単なるミスではなく“生理学的な理由”に基づくものです。
まず、計算より軽い重量しか持てなかったケースについて考えてみましょう。これには次のような原因が考えられます。
- 計算した日と1RMに挑戦した日の体調が違う
- 回数をこなす力(筋持久力)は高いが、最大筋力は低い
- フォームに不安があり、高重量で恐怖心が出た
- 神経系がまだ最大重量に慣れていない
このように、特に初心者~中級者の段階では、筋肉の容量はあっても“最大出力を引き出す技術”が足りないことがあります。つまり「潜在能力はあるけど、発揮できていない」状態です。
一方、計算より重い重量が挙がったという人もいます。これは以下のような背景があります。
- 換算時の回数が少なすぎて、係数の誤差が大きくなった(例:2回や3回)
- 瞬発力や神経系の発達が優れていて、1回だけなら高出力を出せるタイプ
- 精神的に集中し、アドレナリン効果で本来以上の力を発揮した
たとえば、「80kgを3回できたから換算で約90kgの1RM」となっていたのに、実際には100kgを成功させた場合などが該当します。
このような「実際との差異」は、個々の特性やトレーニング歴、そしてその日のコンディションによって起こる“人間らしさ”の表れなのです。
また、RM換算には“平均化されたモデル”を使っているため、万人にぴったり当てはまるわけではありません。ある人にとっては正確な指標でも、別の人にとってはズレることがあります。
たとえば以下のようなケースも考慮しましょう:
- 短距離選手タイプ(爆発力型):1RMは高いがRM換算ではやや低く見積もられる
- 長距離選手タイプ(持久力型):RM換算では高く出るが実際の1RMはやや低め
つまり、「ズレる=間違い」ではなく、「ズレる=個人差の表れ」と捉える視点が重要です。

北野 優旗
「1RM換算と実測の差は、むしろ“今のあなたの特性を映す鏡”です。ズレたとしてもがっかりせず、その理由を探ることで、より深くトレーニングを理解できます。」
気をつけろ!スクワット換算の間違いやすい落とし穴
RM換算は非常に便利なツールですが、その便利さゆえに「過信」や「誤用」によるトラブルが多いのも事実です。特に初心者が数字だけを鵜呑みにすると、オーバーワークやケガの原因になるケースも少なくありません。このセクションでは、スクワット換算を使ううえでよくある失敗や、正しく使うための注意点を徹底解説します。
表:RM換算をめぐるよくあるミスと正しい対策
|
よくある誤解・ミス |
解説 |
正しい対策 |
|
計算された1RMをそのまま目標重量にする |
換算値は「理論値」であり、実力の保証ではない |
計算値の80~90%から始める |
|
疲れている日も同じ回数を強行しようとする |
筋疲労や睡眠不足で1RMは大きく変わる |
体調に応じて“日替わり設定”を取り入れる |
|
回数を妥協して計算に用いる |
フォームが乱れた状態ではデータの意味がなくなる |
「ギリギリまで正確なフォーム」で記録を取る |
|
高重量を無理に1回持ち上げようとする |
急激な負荷は腰や膝を痛めるリスクが高い |
「計算→段階的に近づける」方法で取り組む |
|
数字ばかりに集中してトレーニングがおろそかになる |
「数字=目的」になりがち。本質は成長である |
数値は“指標”であって“目的”ではないと心得る |
RM換算は“筋トレの補助輪”であり、“制御装置”であることを忘れてはいけません。
「RM表通りにできない…」それはあなたのせいではない
RM表の数字通りに重量が挙がらなかったとき、落ち込む必要は一切ありません。というのも、その日のコンディション、ウォームアップ不足、睡眠の質、精神的集中の有無など、パフォーマンスには多くの変数があるためです。
たとえば、普段は100kg×10回できるのに今日は8回で限界だったとしたら、それは「1RMが落ちた」わけではなく、「今日の神経系や身体のスイッチがうまく入っていない」だけということが多いのです。
また、RM換算表に掲載されている値は、あくまで「理想的な条件下での一般値」。あなた個人の身体構造、筋繊維のタイプ、メンタル状態までは反映されていません。
- 睡眠が6時間未満だった
- 食事がいつもより遅れた
- 不安や焦りがあった
- 気温や湿度の影響を受けた
これらはすべて、1RMやRM換算の「ズレ」を引き起こす要因になります。
つまり「RM換算通りにいかない=自分の努力が足りない」ではなく、「今日はそういう日なんだ」と受け入れる視点が大切です。
トレーニングの本質は“継続”と“質の積み上げ”であり、一回の失敗で評価されるものではありません。むしろズレや誤差を通して自分の身体の理解が深まれば、それは失敗ではなく“成長の種”です。
科学的根拠:Sleep deprivation leads to a decline in athletic performance, resulting in impaired neuromuscular coordination, increased injury risk, and delayed recovery in both athletes and non-athletes (Charest and Grandner, 2020). (睡眠不足は運動能力の低下につながり、神経筋協調性の低下、怪我のリスクの増加、アスリートと非アスリートの両方における回復の遅延につながります (Charest and Grandner、2020)。)

北野 優旗
「うまくいかない日があるのは当たり前。それを“データの誤差”と捉えるだけで、モチベーションは大きく変わります。数字はあくまで“あなたのガイド”であって“裁判官”ではありません。」
フォーム崩壊・可動域・スピード:数字の落とし穴を回避する
RM換算で算出した数値が正しくても、フォームや可動域、動作スピードの乱れがあるとトレーニング効果は激減し、ケガのリスクすら高まります。つまり「数字上は完璧」でも「動作が伴っていなければ失敗」と言えるのです。特にスクワットは全身を使う多関節種目であるため、フォームの質が1RM以上に重要です。
よくある問題点として、以下の3点が挙げられます。
- フォーム崩壊:腰が丸まる、膝が内側に入る、猫背になるなどのエラーがRMを過信した際に発生しやすい。
- 可動域の不足:「深くしゃがむ」動作ができていないと、筋肉の最大収縮が起きにくく、1RMの数値が過大評価される。
- 動作スピードの乱れ:反復回数にばかり意識が行き、反動やスピードで“ごまかす”挙上になるケース。
RM換算の精度は「数字の正しさ」だけでなく、「動作の正確性」によって担保されるものです。
たとえば100kgを10回できるとしても、浅いスクワットでスピード重視のフォームなら、正しいフォームで深くしゃがんだ80kg×8回の方が、実際には筋力も安全性も高い場合があります。
以下のチェックポイントで、自分のスクワットフォームが適正かどうかを確認してみましょう。
箇条書き:正しいスクワットフォームのポイント
- バーを背中にのせた状態で背筋が自然に伸びているか
- しゃがむ際、膝とつま先が同じ方向を向いているか
- 大腿骨が床と平行もしくはそれ以下になるまでしゃがめているか
- 挙上時に腰が先に上がったり、背中が丸まったりしていないか
- 動作スピードが一定かつ制御されているか
これらの基準を守れているときこそ、RM換算値に意味があります。逆に、基準を無視した上でのRM数値は、「ただの見せかけの強さ」に過ぎず、怪我のリスクが高いといえるでしょう。

北野 優旗
「RM換算に夢中になりすぎて“フォームを置き去り”にしてしまう方が非常に多いです。数値よりもまず『安全な動作』を最優先しましょう。正しい動きが、数字を“本物”に変えてくれます。」
換算は万能じゃない!プログラム設計における補助的活用法
RM換算は確かに便利な指標ですが、「それだけ」でトレーニングメニューを決めるのは極めて危険です。なぜなら、RM値は“筋力”という一側面しか見ておらず、筋持久力・可動域・柔軟性・フォーム・神経系の発達といった重要な要素を無視してしまうリスクがあるからです。
多くの人が、1RM換算からトレーニングプログラムを「自動的に組み立てられる」と考えますが、それは誤解です。確かにRM換算はベースにはなりますが、以下のような補助的な使い方が最も効果的です。
テーブル:RM換算をプログラム設計に使う具体例
|
トレーニング目的 |
使い方 |
注意点 |
|
筋力向上 |
85~95%のRMで3~5レップ中心のセット設計 |
中央神経系に負荷がかかるため回復重視 |
|
筋肥大(ボディメイク) |
65~80%のRMで8~12レップのボリュームトレーニング |
RM値よりも「効かせる」意識が必要 |
|
筋持久力 |
50~65%のRMで15レップ以上 |
RM換算よりRPE(主観的強度)が重要になる |
|
テクニック向上 |
40~60%のRMでフォーム練習 |
RM値はほとんど参考にならない |
このように、RM換算は「メニュー作成の出発点」であり、「ゴール」ではありません。
また、トレーニング経験の浅い人ほど、1RMを根拠にした重量設定だけではオーバーワークになりがちです。体調や回復度、生活習慣によって、理想的なトレーニング強度は日々変化するからです。
そこでおすすめなのが、「RM換算 × RPE(主観的運動強度)」という組み合わせです。たとえば「今日は85%RMだけど、RPEが9(かなりキツい)だからセット数を減らそう」といった柔軟な対応が可能になります。
さらに、RM換算値は週ごとの成長チェックにも使えます。「先週は80kg×8回だったのが、今週は10回できた」→「1RMが伸びている」と判断できるため、定点観測ツールとしても優秀です。
RM換算の「目的」はあくまで“精密な自己理解”。それをどう活用するかが“実践力”となります。

北野 優旗
「RM換算は“絶対値”ではなく“参考値”。だからこそ、自分の体調・目的・回復度に合わせて活用してください。“数字”と“感覚”のバランスを取ることが、長期的に見て一番の近道です。」
換算データの応用術:ただの数字を“武器”に変える
RM換算は、ただの「計算遊び」ではありません。その数字をうまく活用できる人こそが、効率よく・安全に・継続的に成長していけるトレーニーです。この章では、1RMを起点とした実践的な活用術を紹介し、スクワット換算がどれほど実用的な武器になるかを掘り下げていきます。
目的別に重量設定を調整したり、成長をグラフ化して自己分析したりすることで、「なんとなくトレーニング」から卒業し、「戦略的に鍛える」へと進化できます。
箇条書き:換算データの主な活用ポイント
- トレーニング重量の決定:RM値を基準に65~95%で目的別の重量を算出
- ボリューム管理:週間・月間の総負荷(重量×レップ×セット)を数値で把握
- 進捗の可視化:RM値の推移をグラフ化し、伸び悩み時期を分析
- 回復度の確認:いつもより同じ重量が重く感じる→回復不足のサイン
- メニューのバリエーション作成:低重量高回数期/高重量低回数期の切り替えに活用
適切な重量設定でトレーニング効率UP!
RM換算を使えば、あなたの目的に応じた“最適な強度”を設定でき、無駄のないトレーニングが可能になります。たとえば、筋肥大を狙うなら「1RMの70~80%」の重量で「8~12回×3~4セット」が推奨されます。このとき、RM換算がないと「自分にとっての80%が何kgか?」が不明で、適当に重量を選んでしまいがちです。
RM換算を使えば、例えば1RMが130kgの人は、80%=104kg。これを基準に設定すれば、目的に直結した効率的な負荷管理ができます。逆に、計算せずに「100kgで10回できたからいいや」と続けていると、いつのまにか“楽すぎるトレーニング”になってしまう恐れも。
また、筋力向上を狙うなら85~95%の強度が必要となるため、換算値を把握していないと、いつまでも「中途半端な強度」で伸び悩むことにもなりかねません。
RM値を元にしたゾーン設定(例:85%ゾーン、70%ゾーンなど)を行うことで、明確な意図を持ったトレーニングが可能になり、成長効率も飛躍的に高まります。

北野 優旗
「あなたにとっての“正しい重量”は、換算しないと永遠に見えてきません。成長スピードの早い人は例外なく、数字で管理しています。感覚任せは卒業しましょう。」
筋肥大と神経系強化、目的別にRM数を調整しよう
RM換算の最大の魅力は、「筋力」「筋肥大」「筋持久力」といった異なる目的に応じて、明確にトレーニング強度を調整できることです。この章では、1RMを基にしてどのように目的別のレップ数・重量を設定すべきかを、科学的根拠とともに解説します。
まず、筋トレの3大目的ごとに適切なRMゾーンと重量設定の目安を整理しましょう。
テーブル:目的別のRM使用強度とレップ数設定
|
目的 |
1RMに対する使用重量 |
推奨レップ数 |
主な適応 |
|
神経系強化(最大筋力) |
85~95% |
1~5回 |
筋出力・瞬発力 |
|
筋肥大(筋肉量UP) |
65~80% |
6~12回 |
筋線維肥大 |
|
筋持久力向上 |
50~65% |
13回以上 |
持久力向上 |
このようにRM換算は、目的に応じた“強度の使い分け”を明確にできる科学的指標なのです。
たとえば、「見た目を変えたい」「体を大きくしたい」という人は、筋肥大を目的にすべきなので、1RMの70~80%で8~12回の設定がベスト。逆に、パワーリフターやアスリートで「力を強くしたい」人は、85%以上で1~5回の高強度・低回数トレーニングが主流です。
さらに、神経系強化と筋肥大はトレーニングメニューとして相互に切り替えて使うことで、「筋肉のサイズ」と「出力」の両方を高める複合的な成長が期待できます。
また、回数と重量の組み合わせを変えるだけで、体感強度や成長ポイントがガラリと変わるのもポイント。たとえば、70%の重量で12回できたなら、同じ重量でも6回しかできなかった頃と比べて筋持久力が大きく向上していることになります。つまりRM換算は、成長を“実感”ではなく“証明”するための数字でもあるのです。
このように、1RM換算は「メニュー設定」にとどまらず、「トレーニングの進捗確認」や「適切なスイッチング」など、戦略的な筋トレを支える基盤となります。

北野 優旗
「目的に合わせてRMの使い方を変えるだけで、成果の出方が劇的に変わります。逆に、目的とズレた使い方をしていると、いくら頑張っても“報われない筋トレ”になります。1RMを、ただの数字で終わらせないでください。」
記録管理や成長実感の可視化にも活用しよう
RM換算のもう一つの大きな利点は、自分のトレーニングの成果を「見える化」できることです。これは特に中級者以降において重要で、成長のペースが鈍化する時期に「過去の自分と比較する」ことでモチベーション維持につながります。
RM換算を活用した記録管理には、次のような実用的なメリットがあります。
箇条書き:RM換算で記録管理をするメリット
- 成長の軌跡を数字で確認できる 数カ月前の1RMより現在の1RMが何kg増えたかが明確になる。
- プラトー(停滞期)の分析に使える 1RMが伸びない時期に「レップ数は増えているか?」などのデータが役立つ。
- 過去と現在の負荷設定を比較できる 以前と同じRM重量でも回数が増えているなら、成長の証。
- 目的別に記録を分けられる 筋肥大目的・筋力向上目的などで記録の意味合いを整理できる。
- 自信と継続意欲につながる 数字の積み上げが自己肯定感と目標の明確化につながる。
特に初心者のうちは“重さの変化=成長”という単純な認識で十分ですが、中級者以降はRM換算による複合的な記録管理が必要になります。
たとえば、「今月は100kg×8回だったのが、来月は10回できた」→「1RMが伸びた」というように、重量だけでなく“回数の変化”からも進捗が見えるのです。 また、「先月の1RM=110kg、今月=115kg、でもベルトなしで挙げられた」など、フォームや補助具の有無などの記録もRMと一緒に残しておくと精度が高まります。
さらに、スマートフォンのトレーニングアプリやGoogleスプレッドシートなどを活用すれば、自分専用の「筋力成長グラフ」も作成できます。これにより、数字として客観的に進化を確認できるため、停滞期にも冷静に分析し、無駄な不安や焦りを防ぐことができます。
数字で証明された成長は、他人と比較する必要がなくなり、自分だけの成功指標となります。
科学的根拠:Monitoring Training Load to Understand Fatigue in Athletes(アスリートの疲労を理解するためのトレーニング負荷のモニタリング)

北野 優旗
「成長実感がなくなってきたとき、数字の記録は“過去の自分からのエール”になります。RM換算は“未来の自分への贈り物”として、ぜひ習慣化してください。」
実は消費カロリーもわかる?スクワット×METsの意外な活用
多くの人が見落としがちですが、スクワットは筋力アップや筋肥大だけでなく、「消費カロリー」という面でも非常に優れたトレーニングです。しかも、この消費カロリーはRM換算とともに、METs(Metabolic Equivalents:代謝当量)という指標を使うことで「数字」で把握することが可能になります。
つまり、筋トレと有酸素の“中間的存在”として、スクワットはダイエットやボディメイクにとっても超優秀な種目なのです。
筋トレと有酸素の架け橋:エネルギー換算の裏話
METsとは、身体活動による代謝量を示す単位で、安静時の代謝を「1」として、何倍のエネルギーを使うかを表します。この数値を用いることで、「スクワットを〇分行えば何kcal消費するか?」を正確に算出できるようになります。
一般的に、スクワットのMETsは4.0~8.0とされており、以下の条件によって変化します。
- 4.0 METs:軽度なスロースクワット、自重でゆっくり
- 6.0 METs:中強度のスクワット、ダンベルあり・10~15レップ程度
- 8.0 METs以上:高重量・ハイレップ・バーベル使用のスクワット
では実際にどのくらいのカロリーを消費するのでしょうか?計算式は以下の通りです:
消費カロリー(kcal)= METs × 体重(kg) × 運動時間(h)
例)体重60kgの人が、中強度(6.0 METs)のスクワットを30分行った場合:
6.0 × 60 × 0.5h = 180kcal消費
これは、軽いジョギング(METs 6.0)や、早歩きとほぼ同等の消費量です。つまり、スクワットは筋力向上と同時に“有酸素運動的”な脂肪燃焼効果も期待できるのです。
さらに、RM換算を用いて適切な負荷(1RMの60~75%)でのボリュームトレーニングを行えば、運動強度が高まる分、消費カロリーもアップ。加えて、EPOC(運動後過剰酸素消費)の効果で、トレーニング後も代謝が上がり続けるというボーナス付きです。
「脂肪を燃やしながら筋肉もつけたい」??そんな欲張りな目標にも、スクワットとRM換算の組み合わせは完璧に応えてくれます。
科学的根拠:The Compendium of Physical Activities Tracking Guide(身体活動追跡ガイド大全)

北野 優旗
「筋トレは消費カロリーが少ないと思われがちですが、スクワットのような全身運動では、有酸素運動に匹敵するカロリー消費が見込めます。METsとRMを掛け合わせて、“燃やして、鍛える”が実現できます。」
よくある質問
スクワットのRM換算に関して、初心者から上級者まで多くの方が疑問に思うポイントをまとめました。以下は特に検索ボリュームが多く、現場でもよく寄せられる質問とその回答です。
Q1. 実測の1RMと換算の1RM、どちらが正確ですか?
- 実測の方が理論上は正確ですが、換算の1RMは安全性と再現性の面で非常に優れています。とくに初心者やフォームに不安がある人には、換算値を基準にしたプラン作成をおすすめします。
Q2. 換算式はいくつかあるけど、どれを使えばいいの?
- 初心者~中級者にはEpley式がおすすめです。 理由は計算がシンプルで、精度もバランスが良いためです。上級者になると、Brzycki式やLombardi式を比較して使うケースもあります。
Q3. スクワット換算は自重でも使えますか?
- 使えます。片足スクワット(ブルガリアン・スプリットなど)を用いれば、自重でもRM換算が可能です。回数や負荷の変化から1RM相当を推定し、プログレッションの目安にできます。
Q4. 筋肉痛があるときでもRM換算していい?
- おすすめしません。筋肉痛は回数や出力に影響するため、正確な数値が出にくくなります。換算を行う日は「体調が安定していて、コンディションが良好」なときを選びましょう。
Q5. 女性でもスクワット換算は使うべきですか?
- もちろんです。女性でも1RM換算を活用することで、無理なく安全に適切なトレーニング負荷を設計できます。特に筋力が付きにくいとされる部位に対して、数値で追えるのは非常に有効です。
Q6. スクワット換算の記録はどこに残せばいい?
- ノートやExcelも良いですが、Googleスプレッドシートやアプリ(例:Strong、FitNotes)がおすすめです。可視化やグラフ化がしやすく、過去の記録と比較するのも簡単です。
Q7. 同じRMでも疲れや日によって違うのはなぜ?
- それが「人間の体」の特徴です。RM換算は目安であり、毎日の状態により±5~10%の誤差は普通に起こります。気にせず「その日の最善」を尽くすことが大切です。
まとめ
スクワット換算は、単なる「数値の遊び」ではなく、あなたのトレーニングを科学的に設計し、確実に成長へ導くための強力なツールです。この記事を通じて、RM換算の基本的な仕組みから活用法、注意点、そして消費カロリーや記録管理まで網羅的に理解していただけたはずです。
まず押さえておきたいのは、RM換算は「最大筋力を予測する方法」であり、1回挙げるリスクの高い重量を実際に試すことなく、自分の筋力を安全に評価できる手段だということ。初心者でも簡単な計算式やオンラインツールを使って、精度の高いトレーニング設計が可能になります。
また、体重比で見る筋力レベルや、回数ごとの換算係数を用いることで、自分の現在地を明確にできるのもRM換算のメリットです。これにより、「目標設定が曖昧」「伸びている実感がない」といった課題から解放されます。
一方で、RM換算は“万能”ではなく、“補助的な指標”であることを忘れてはいけません。フォーム・可動域・精神状態・疲労度などがRMに影響を及ぼすため、誤差が生じるのは当然のことです。それでも、自分の筋力を“見える化”し、日々の成長を数値で感じるためには欠かせない道具であることもまた事実です。
さらに、RM換算はメニュー作成の根拠になるだけでなく、カロリー消費の計算や、筋肥大・神経系強化・筋持久力といった目的別トレーニングへの応用にも対応できる“マルチな情報資産”です。
記録を取り続ければ、あなたの筋力グラフは「成長の証明書」となります。他人と比べるのではなく、「昨日の自分」と向き合う姿勢こそが、真のトレーニング成功への道なのです。
RM換算の活用で得られる主な効果:
- トレーニングの計画性が高まる
- 進捗が数字で確認でき、モチベーション維持が容易になる
- 自分の筋力レベルを体重比で客観評価できる
- トレーニング目的ごとの強度を最適に設定できる
- 無理・無駄・怪我のリスクを大きく減らせる
最後に、RM換算の最も重要な価値は、“自分の体と深く向き合う手段”であるという点にあります。
数字に振り回されるのではなく、数字を使って理想の自分を設計していく。 その先にあるのは、より安全で、より戦略的で、そして成果が伴う筋トレ人生です。
科学的根拠でサポートされたスクワット換算。 あなたのトレーニングの質を、今すぐ“計算”で変えていきましょう。
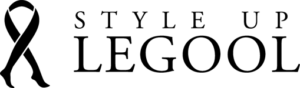



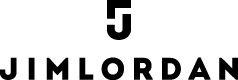





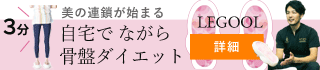
コメント