「シャトルランって平均どれくらいが普通?」「自分は体力的に大丈夫なのかな?」そんな疑問を持つ方に向けて、この記事ではシャトルランの平均回数から、記録の伸ばし方、面白トリビアまでを網羅的に解説します。文部科学省が発表する体力テスト基準や最新データに基づき、初心者にもわかりやすくまとめているのでご安心ください。この記事を読めば、シャトルランの全体像と自分の立ち位置が明確にわかります。
こんな人におすすめの記事:
- シャトルランの平均記録が気になる学生・親御さん
- 自分の記録が「普通」なのかを知りたい人
- スポーツ推薦や進路に向けて得点を上げたい部活生
- 運動が苦手で、克服したいと感じている人
- 学校や教員で子どもに正しく指導したい立場の方
目次
シャトルランって何者?まずは基本から理解しよう
シャトルランは、正式には「20メートルシャトルラン」と呼ばれ、体力測定やスポーツ競技の基準にも使われる持久系の運動能力テストです。名前だけは知っていても、なぜ行うのか、どんな意味があるのかまで理解している人は意外と少ないかもしれません。このセクションでは、シャトルランの基本的な仕組みと目的をしっかりと把握しましょう。
そもそもシャトルランとは?ルールと目的を解説
シャトルランは、20メートル間隔に置かれた2点間を音に合わせて往復し続ける持久力テストです。音のテンポが徐々に速くなることで、被験者の最大酸素摂取量(VO~max)や心肺持久力を間接的に評価する目的があります。
つまり、シャトルランは“走るスタミナ”だけでなく、心肺機能やリズム感も問われるテストです。
この種目は1980年代にカナダの体力評価機関により導入され、日本では2000年代以降、全国体力・運動能力調査(いわゆる「体力テスト」)の中に組み込まれるようになりました。
- テストの進行
- スタート音に合わせて20m先のラインまで走る
- ライン到達後、反対側へ折り返し
- 一定時間ごとにテンポが速くなる
- 走り続けられなくなった時点で終了
- 目的と評価対象
- 心肺持久力の測定(VO~maxと相関あり)
- 運動習慣の評価
- 若年層の基礎体力レベルの把握
科学的にも、VO~maxとの相関が高いとされており、実際の論文でも以下のような根拠があります。
このように、シャトルランは単なる体育の授業の一環ではなく、医学的・スポーツ科学的にも有意義なテストとされているのです。
なぜ体力テストに取り入れられているのか?
シャトルランが学校教育の体力テストに広く使われる理由は、「簡便性」「安全性」「評価のしやすさ」にあります。
シャトルランは特別な器具を使わずに、大人数でも公平に実施できるテストです。
全国体力テストにおける20mシャトルランは、文部科学省の「新体力テスト実施要項」によって、毎年数百万人が受験しています。
【導入のメリット】
- 公平性が高い:誰でも同じ条件で実施可能
- 記録が数値化される:体力レベルを客観評価
- 部活や体育以外でも活用可:習慣づけのモチベーションに
また、学力との相関が指摘される研究もあり、身体的な持久力の高さが学習能力や集中力とも関連しているという知見もあります。
参考論文:Physical fitness, obesity, and academic achievement in schoolchildren(児童の体力、肥満、学業成績)
つまり教育的な側面から見ても、「なぜシャトルランを行うのか」には納得できる理由があるのです。
文部科学省が定める基準とは?
文部科学省は「新体力テスト」において、学年・性別ごとの評価基準を設定しており、それぞれの記録はA~Eの5段階で判定されます。
この基準により、全国どこでも同じ物差しで子どもの体力レベルを評価できるのです。
以下のような表が、実際の新体力テスト評価基準に沿って作られています:
|
学年 |
性別 |
A評価 |
B評価 |
C評価 |
D評価 |
E評価 |
|
小5 |
男子 |
80回以上 |
70回以上 |
55回以上 |
40回以上 |
39回以下 |
|
小5 |
女子 |
60回以上 |
50回以上 |
40回以上 |
30回以上 |
29回以下 |
|
中1 |
男子 |
90回以上 |
75回以上 |
60回以上 |
45回以上 |
44回以下 |
|
中1 |
女子 |
70回以上 |
60回以上 |
45回以上 |
35回以上 |
34回以下 |
上記の数値は毎年微調整される可能性があるため、最新の資料を参照することが大切です。

北野 優旗
「シャトルランは努力の分だけ数字に表れるテストです。1日5分のランニングでも、継続すれば確実に記録アップにつながりますよ。まずはルールと目的を理解することから始めましょう!」
【最新データ】シャトルランの平均回数一覧!
シャトルランの平均回数は、年齢・性別・学年によって大きく異なります。特に学校教育現場で重要視される体力テストにおいては、統計データが毎年更新されており、自分の記録がどの位置にあるのかを知ることができます。このセクションでは、最新のデータをもとにした「年齢別・性別平均」を徹底解説していきます。
小学生・中学生・高校生・大学生・社会人の平均値
シャトルランの回数は、文部科学省が毎年実施する「全国体力・運動能力、運動習慣等調査(通称:体力テスト)」の結果から読み取れます。下記の表は2023年調査データをベースに作成したもので、小学生から社会人までの平均記録をまとめたものです。
平均回数は年齢や性別によって明確に差が出るため、自分の年齢層の中での位置を把握することが大切です。
|
年齢層 |
男性の平均回数 |
女性の平均回数 |
|
小学5年生 |
約63回 |
約48回 |
|
中学1年生 |
約78回 |
約63回 |
|
高校1年生 |
約82回 |
約66回 |
|
大学生(18~22歳) |
約87回 |
約70回 |
|
20代社会人 |
約74回 |
約58回 |
|
30代社会人 |
約67回 |
約54回 |
|
40代社会人 |
約60回 |
約49回 |
|
50代社会人 |
約52回 |
約43回 |
上記はあくまで全体の平均値であり、個人差や生活習慣による違いも大きいため、参考指標として活用しましょう。
参考資料:文部科学省「令和5年度 全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果」
また、年齢が上がるにつれ筋力や持久力が自然と衰えるため、社会人以降は記録の低下は避けられません。しかし、定期的な運動である程度は維持可能です。
男女別・年齢別の平均比較グラフ
男女差は明確に存在し、特に思春期以降の体格差や筋力差が反映されています。また、平均記録には生活習慣や部活動の有無、学校ごとの体育の取り組み方の違いも影響しています。
つまり、平均の記録だけで自分を評価するのではなく、日常的な運動習慣とセットで考えることが重要です。
- 男性は心肺持久力・筋力ともに優位で、記録が高くなる傾向
- 女性は10代前半でピークを迎えやすいが、習慣次第で維持可能
- 小学生時点での体力習慣が中高生以降に強く影響する
ここで興味深いデータとして、同じ年齢層でも都市部と地方で若干の差があることも指摘されています。特に外遊びの機会が減った都市部の子どもほど、平均回数が低く出る傾向にあります。
さらに、スポーツ庁が公開したデータによると、2020年以降の外出制限やオンライン授業の影響により、子どもの体力レベルが一時的に下がっているとの報告も。
これらのデータをもとに、自分の体力が「今どの位置にあるのか」を知り、必要に応じて対策を講じることが重要です。
2020年以降の傾向変化とその背景
コロナ禍を境に、シャトルランの平均値にも大きな変動が見られました。外出自粛や体育授業の制限により、特に小学生・中学生の体力が低下したという統計があります。
2020年~2022年にかけて、10代のシャトルラン平均は約10~15回低下したという報告も存在します。
主な背景は以下の通りです:
- 体育授業・部活動の中止:体力維持の場が減少
- 外遊びの減少:特に都市部では顕著
- ストレス・不安の影響:モチベーション低下
文部科学省もこの影響を受けて、2023年度から運動時間や生活習慣の見直しに関する施策を拡大しています。例えば「毎日60分以上の運動を推奨する指導ガイドライン」などが各教育機関に配布されています。
こうした背景を知っておくことで、「自分の記録が低いからダメだ」と短絡的に思うのではなく、環境のせいもあるという広い視野で考えることができるでしょう。

北野 優旗
「平均記録を知ることは大切ですが、そこに一喜一憂しすぎる必要はありません。1年前より成長しているか?を指標にすることで、モチベーションを高く維持できます!」
あなたの記録はどのレベル?基準と評価チャート
シャトルランの記録を見て「平均より上だった!」と喜ぶ人もいれば、「下だった…」と落ち込む人もいます。しかし、記録そのものは“通過点”であり、大事なのは自分がどのレベルにいて、どのように向上を目指せるかです。このセクションでは、評価チャートや全国ランキングを使って、自分の立ち位置を視覚的に理解できるように解説します。
平均未満・平均以上・上級者の目安とは
シャトルランでは、一般的に以下のような回数で評価ランクが分類されることが多いです。これらは、各学年や年齢層の体力テスト基準やスポーツ庁の報告をベースにまとめた参考値です。
「平均以上だから満足」ではなく、「次のレベルに挑戦できるか」が重要な視点です。
評価チャート(高校1年男子を例に)
|
評価ランク |
回数 |
体力レベルの目安 |
|
上級者(A) |
100回以上 |
部活動などで積極的に運動している人 |
|
平均以上(B) |
80~99回 |
一般的な体力を上回る良好なレベル |
|
平均(C) |
70~79回 |
標準的な体力を有するレベル |
|
平均未満(D) |
50~69回 |
やや運動不足、改善が望ましい |
|
低体力(E) |
49回以下 |
体力向上が急務なレベル |
※女子の場合は平均点がやや低くなり、各ランクの数値が10~15回ほど少なくなります。
このように、自分の現在の記録と照らし合わせることで、どのレベルにいるかを簡単に把握できます。もちろん「D→C」「C→B」といったように、段階的な成長を目標にするのが現実的かつ効果的です。
パフォーマンスの継続的な記録は、モチベーション維持に大きく寄与します。
全国ランキングと自分の立ち位置をチェック
全国レベルで見ると、部活動を行っている運動部の学生やアスリート志望者の記録は飛び抜けています。では、自分の記録は全国の中でどれくらいの位置にあるのでしょうか?
以下は、スポーツ庁の報告をもとにした「全国成績分布イメージ」です。
- 上位5%: 男子で120回以上、女子で100回以上
- 上位10~20%: 男子で100~119回、女子で80~99回
- 中央値(平均): 男子で75~85回、女子で60~70回
- 下位20%未満: 男子で60回以下、女子で50回以下
このように、「平均よりも少し上か下か」ではなく、全国の分布で自分がどこに位置するのかを知ることは、非常に有意義なモチベーションになります。
あなたが今の立ち位置を客観視することは、未来の可能性を正しく見極める第一歩になります。
また、自分の通う学校の平均や県別データなども存在するため、それらを参考にするとよりリアルな比較ができます。
スポーツ推薦に有利?高得点のメリットとは
特に中学・高校生にとって、シャトルランの成績は内申書や推薦基準にも影響を及ぼす場合があります。たとえば、運動部への推薦やスポーツ系高校・大学進学時の参考データとして活用されることもあります。
高得点を記録することで得られるメリットは以下のとおりです:
- 内申点の向上: 体育の評価基準に含まれる
- スポーツ推薦の参考資料: 全国大会出場者などは体力データを提出することも
- 自信と信頼の獲得: クラス内での信頼度アップ、自己肯定感の向上
- 進路の幅が広がる: スポーツ系専門学校、消防・警察試験などにも応用可能
もちろん、記録がすべてではありませんが、体育の授業や部活動に真剣に取り組む姿勢は、記録以上に評価される点でもあります。
高記録を目指す過程そのものが、他の面にも良い影響をもたらします。

北野 優旗
「“自分に勝つ”という気持ちで挑むことが、記録以上に価値があります。数字にとらわれすぎず、努力の過程を楽しんでください!」
シャトルランの記録を伸ばすための戦略
シャトルランで記録を伸ばすには、ただ“走る練習”をするだけでは不十分です。持久力・心肺機能・フォーム・メンタル、さらには当日のコンディションまでが複雑に絡み合って記録に反映されます。本セクションでは、科学的根拠に基づいた「本当に効果がある戦略」に絞ってご紹介します。
筋持久力と心肺機能を高めるトレーニング法
シャトルランは、持久走と違いインターバル形式(走って止まってまた走る)で行うため、単なる長距離走の持久力とは異なる力が必要です。そこで重要になるのが以下の2軸の強化です。
「筋持久力」と「心肺機能」のバランス強化が、記録向上のカギです。
効果的なトレーニングメニュー(週3回目安)
|
種類 |
トレーニング例 |
目的 |
|
インターバルトレーニング |
20m×10本(徐々に本数増加) |
シャトルランに特化した有酸素負荷 |
|
タバタ式HIIT |
スクワット・ジャンプなど20秒×8セット |
筋持久力+心肺強化 |
|
LSD(長時間ゆっくりラン) |
30分以上の軽めのジョグ |
脂肪燃焼・心拍数調整 |
|
筋トレ(自重) |
スクワット、ランジ、プランクなど |
下半身と体幹強化で走行安定 |
※ポイントは「20mの距離」に体を慣らすこと。長距離走とは違い、ストップ&ゴーの反復力がものを言います。
特に注目されているのが「タバタトレーニング(Tabata HIIT)」です。20秒の全力運動+10秒休憩を4分間繰り返すことで、短時間でVO2maxを高められると実証されています。
直前の食事・水分補給の正しい取り方
トレーニングの成果を最大限発揮するには、当日の「食事と水分補給」の最適化も重要です。特に“エネルギー切れ”や“脱水症状”がシャトルランの失速要因になるため、直前の栄養戦略も侮れません。
ベストなパフォーマンスには、炭水化物+水分+ミネラルの適切な補給が不可欠です。
実施当日の食事・飲み物のポイント
- 2時間前までに消化の良い主食を摂取(おにぎり、うどんなど)
- 運動30~60分前にはバナナやゼリー飲料でエネルギー補給
- 水分は「一気飲みせず」こまめに分けて摂取(500mlを2回に分けるなど)
- 汗で失われるナトリウム・カリウムも意識し、スポーツドリンクを活用
避けたい食べ物は、脂質の多い揚げ物や消化の悪い食物繊維です。満腹状態で走ると横腹痛の原因にもなるので、食べ過ぎも要注意。
記録が伸びない原因はトレーニング不足ではなく、「栄養不足」だったという例も珍しくありません。
失速しない!ペース配分のコツとは
シャトルランは後半になるほど音の間隔が短くなり、気付かないうちに限界が近づいてきます。スタート直後に飛ばしすぎると後半でバテてしまい、逆に慎重になりすぎても「感覚に遅れる」という結果に。
前半の余裕が後半の持続力を生む。「意識的なペース管理」が勝負を分けます。
ペースコントロールの具体策
- 最初の20~40回までは「1テンポ余裕ある速度」で入る
- 中盤(40~80回)はフォームを意識しながら「呼吸を一定に」
- 終盤(90回~)は「カウントダウン戦略」=10回ごとに自分にご褒美設定
- 周囲の人と比較せず、「音だけに集中する」意識を持つ
特に初心者は、周囲のペースに引っ張られて序盤で疲れてしまいがちです。シャトルランは個人戦。「自分のリズムを守ること」が、最終的な記録につながります。
息が乱れ始めたら、“鼻呼吸+深呼吸”で一度リセットすることが有効です。

北野 優旗
「練習時は“スローモーションでも最後まで完走する”意識で臨みましょう。本番では焦らず、“自分にとっての音との対話”を楽しんでください!」
年代別・目的別のトレーニングメニュー例
シャトルランで記録を伸ばすための方法は「年齢」や「目的」によって異なります。小学生と社会人では体力レベルも生活習慣もまったく異なるため、それぞれに最適なメニューを実践することが大切です。この章では、「子ども」「中高生」「社会人」に分けて具体的なトレーニング例をご紹介します。
子ども向け:遊びながら持久力アップ
成長期にある小学生にとって、厳しいトレーニングは逆効果になることも。まずは「楽しく体を動かす」ことが持久力育成の第一歩です。
「走る=楽しい」を習慣化することが、記録アップに直結します。
- 鬼ごっこ・だるまさんが転んだ: 変則的なダッシュ&停止でシャトルランと同じ動きを遊びながら実現。
- リレー形式の遊びラン: 20mを往復するレースで、自然とスピードとスタミナを両立。
- ストップ&ゴー遊び(信号ゲームなど): 反応速度と集中力も養える。
無理な負荷をかけるよりも、「飽きずに続けられる運動」が最大の鍵です。保護者が一緒に遊ぶことで、モチベーションアップにもつながります。
中高生:学校テスト対策プログラム
中学生や高校生では、本格的な体力測定対策として、シャトルランに特化した練習も効果的です。部活に所属していない人でも、週2~3日の軽い取り組みで記録は伸ばせます。
「少ない時間でも効率よく鍛える」ことが、中高生の成功パターンです。
- 20mインターバル走: 走る→止まる→走るの基本動作を週2回以上。回数を徐々に増やす。
- ステップ走+プランク: 足腰と体幹を一緒に鍛えることでバテにくくなる。
- シャトルラン模擬テスト: 本番を想定して月に1度テスト形式で練習する。
さらに、部活の内容に合わせて有酸素・無酸素のバランスを意識できるとベスト。特にバスケ・サッカー・バレーなど「断続的なダッシュ」が多い競技経験者は、有利です。
社会人:体力維持・健康管理のために
仕事や家庭の事情でなかなか時間がとれない社会人でも、日常生活の中で体力を維持する方法はあります。目標は「記録」よりも「呼吸が乱れない体作り」です。
「継続可能な軽運動こそ、最大のトレーニング」になります。
- 通勤ウォーキング+階段利用: 1日合計6000~8000歩を目指す。
- ラン&ウォーク(10分ずつ交互): 時間がない日はこれで十分。
- 週末ジョグ+体幹トレ(15分): 習慣化しやすいパターン。
また、シャトルラン自体を“楽しむ”という感覚で取り組むのも有効です。仲間と一緒に測定して競い合う、というスタイルは大人にもおすすめ。
「目指せ◯回!」よりも、「今週も継続できた」が喜びになる環境を作りましょう。

北野 優旗
トレーニングは年齢や目標で内容が変わります。大切なのは「その人のペース」で進めること。無理のない範囲で継続することが、最大の成果につながります。
シャトルランにまつわる面白トリビアと裏話
シャトルランというと「苦しい」「キツい」という印象が強いかもしれませんが、実は奥深くて面白いトピックがたくさんあります。世界記録や伝説の指導法、他国との違いなど、知るとちょっと好きになる(かもしれない)シャトルランの裏話をたっぷりご紹介します。
「走るのがイヤ」な人も、思わず友達に話したくなるような雑学が満載です。
世界最強は何回?驚異の記録に迫る
まずは気になる“人類の限界”から。
シャトルランの最高記録は、なんと270回以上という報告もあります。これは一般的な体力テストでの計測上限(多くは120回前後)をはるかに超える数字で、競技アスリートや軍隊式トレーニングを受けている層で見られるようです。
通常の学生テストでは200回を超えた時点で「非常に優秀」とされます。
伝説の記録(国内外)
- 日本記録(非公式): 某高校生男子が215回(体育教師談)
- カナダ軍士官候補生: 訓練時に260回到達
- ギネス認定: 公式ではないが、ネット上には270回の記録動画も存在
このように、記録の“天井”は意外と高く、鍛えればここまで到達できる可能性があるということです。
限界を突破するために必要なのは、肉体だけでなく“音に対する冷静な判断力”とも言われています。
伝説の体育教師が語る「シャトルランあるある」
長年シャトルランを見てきたベテラン体育教師たちから聞いた“あるある”も、ちょっと面白い。
- あるある①:音楽のテンポが変わると、急にやる気をなくす子が出る
- あるある②:「あと何回?」と聞く子ほど、意外と長く走る
- あるある③:「一緒に走ってくれる先生」がいると、記録が伸びる
- あるある④:ラスト1回だけ全力ダッシュする謎の勢い見せる子がいる
- あるある⑤:転んでも立ち上がって続ける子はクラスのヒーローになる
シャトルランは“努力する姿が見える”数少ないテストだと言われています。
一緒に走って応援したり、音をカウントしてくれる仲間の存在が、思わぬ力を引き出すことも多いようです。
他国との比較:日本のテスト文化って特殊?
実はシャトルラン(Beep Test)は、日本だけでなく世界中の教育現場や軍・警察訓練でも活用されています。しかし、その運用方法や評価基準は国によって大きく異なります。
海外での活用例
- オーストラリア: 小学校~大学まで公式テストとして導入
- イギリス: 軍・消防・警察の採用試験でも実施される
- アメリカ: 学校ではあまり一般的ではなく、体育は自己選択制
日本のように全国統一でテストを行い、全学年の平均データを公開する国は非常に稀です。
この背景には、日本独特の「体力=教育の重要指標」という文化があると言えるでしょう。特に「体育成績が内申に直結する」点は、海外ではほとんど見られません。
また、日本のように“順位を付ける”よりも、“成長を見る”ことにフォーカスする国も増えており、今後は日本の体力テストもアップデートされる可能性があります。
海外では“自己ベスト更新”が何よりも評価される傾向にあり、心理的負担が少ないのが特徴です。

北野 優旗
「嫌われがちなシャトルランですが、視点を変えれば“ゲーム感覚”で楽しめる種目。記録よりも、努力と継続の価値に目を向けて!」
シャトルランと他の体力テストとの違い
体育の授業や体力測定では、シャトルラン以外にも様々な種目が実施されます。たとえば「長距離走」「持久走」「ステップテスト」など。しかし、それぞれには明確な違いがあり、同じ“体力”を測る種目でも測定している要素は異なります。このセクションでは、シャトルランが他の種目とどう違うのかをわかりやすく解説していきます。
20mシャトルラン vs 長距離走の違い
まず多くの人が疑問に感じるのが、「シャトルランって結局、長距離走と同じじゃないの?」という点。結論から言うと、目的も測定される能力も全く異なります。
主な違いを比較した表
|
項目 |
シャトルラン |
長距離走(1500mなど) |
|
測定形式 |
往復走(20m) |
周回走(400mトラックなど) |
|
負荷の変化 |
段階的に強くなる |
一定のスピード維持 |
|
評価対象 |
心肺機能、瞬発的持久力、敏捷性 |
有酸素持久力、ペース維持力 |
|
精神的特徴 |
音によるプレッシャー |
自分との闘い(単調) |
|
トレーニング効果 |
インターバル的要素が強い |
有酸素運動の持続力強化 |
シャトルランは“変化に対応する力”が求められ、単なる持久走とはまったく異なる負荷がかかるテストです。
また、心理的なプレッシャーの種類も違います。シャトルランは「音に間に合うか」というプレッシャーが常にあるのに対し、長距離走は「自分とのペース勝負」となります。
持久走が得意でもシャトルランは苦手?
意外と多いのが、「マラソンは得意なのに、シャトルランは全然ダメだった…」というケース。これは、シャトルラン特有の要素が影響しています。
- ストップ&ゴーの動作: 単調なペースで走り続けるのではなく、折り返しでスピードの再加速が必要
- ターン時の減速と加速: 毎回方向転換で脚部の筋持久力が削られる
- ペースアップの連続: 走るテンポが一定ではないため、心拍数が早い段階で乱れる
つまり、マラソン型の「ゆっくり長く」は通用しないテストだということです。
そのため、長距離走で優秀な成績を出している人でも、シャトルランで記録が伸び悩むのはまったく不思議ではありません。
対策としては、「折り返しを意識した走行練習」や「加速・減速に対応できる脚筋の鍛錬」などが有効です。
あなたに合った体力測定の選び方
最後に、目的別におすすめの体力測定を紹介します。
体力測定は目的に応じて使い分けることで、より正確に“自分の強み・弱み”を知ることができます。
- 心肺機能を正確に知りたい: シャトルラン or ステップテスト
- スタミナ持久力を測定したい: 長距離走(1500m・3000mなど)
- バランス型の総合体力: 体力年齢測定(握力・反復横跳び・立ち幅跳び含む)
- 競技別に特化した能力: Yo-Yoテスト(サッカーなどのアスリート向け)
また、複数のテストを組み合わせることで、より立体的に自分の体力像を把握することができます。
“自分に合ったテスト”を知ることで、目的に合わせたトレーニング設計が可能になります。

北野 優旗
「自分の得意不得意を知ることで、トレーニングの“効率”が大きく変わります。不得意な種目も、“なぜ苦手なのか”がわかれば、克服のヒントが見つかりますよ!」
よくある質問
ここでは、シャトルランに関して読者の方々からよく寄せられる質問をまとめて回答します。初めての人も、記録を伸ばしたい人も、ここで疑問を解消してから挑戦してみてください。
1回ごとの距離や速度は?
シャトルランは1往復20メートルの距離を、電子音の間隔に合わせて走るテストです。速度は段階的に速くなり、初期は約8.5km/h、最終段階ではおおよそ13~15km/hにも達します。
1段階ごとに速度が増していくインターバル形式が、心肺への負荷を徐々に高める仕組みになっています。
シャトルランで倒れそうになったら?
無理は禁物です。途中で息苦しさや立ちくらみ、吐き気などを感じたら、すぐに中止しましょう。シャトルランは根性試しではなく、自分の現在の体力を測るためのテストです。
特に以下のような兆候が出たら、危険信号です:
- 動悸や不整脈を感じる
- 呼吸困難になる
- めまいがする
- 嘔吐感がある
身体が出す“やめどきのサイン”には必ず従いましょう。
体力がない人はどう練習すればいい?
運動初心者や、普段あまり走っていない人は、まず「走ることに慣れる」ことからスタートしましょう。いきなりシャトルラン形式で練習する必要はありません。
おすすめは以下のステップです:
- まずはウォーキング10分から開始
- 20mの折り返し走をゆっくりペースで実施
- 走行距離よりも“止まらず続ける”を意識
- 慣れたらステップアップで回数増加
“自分のペースで続けること”が、最も記録に繋がるトレーニングです。
「記録に残るのが恥ずかしい」と思ったら?
気持ちはよくわかります。しかし、体力テストの本質は「他人との比較」ではなく、「自分の成長」を見ることにあります。誰にでも得意・不得意はあるので、“今の自分”を知ることがすべてのスタート地点です。
また、先生や周囲の友達も、実はそんなに他人の回数を見ていません。記録が少なくても、真剣に取り組んだ姿勢は必ず評価されます。
「去年より少しでも伸びた!」が、一番カッコいい記録です。
どんな靴や服装で走るのがベスト?
シャトルランはストップ&ゴーの動作が多いため、滑りにくくグリップ性の高いシューズがおすすめです。また、汗をかくので吸湿性と速乾性のあるウェアを選びましょう。
- ソールがすり減っていないトレーニングシューズ
- 軽量かつ通気性の良いスポーツウェア
- 体育館ならインドア向けの靴がベスト
服装の快適さは、記録を伸ばすための“隠れた武器”です。
学校での順位が悪くて落ち込んだらどうする?
順位はあくまで“その場での相対的な評価”にすぎません。大切なのは、自分がどれだけ努力し、どれだけ改善できたかという“自己成長の視点”です。
また、ほかの種目(柔軟性・筋力・瞬発力)で得意分野を持っている人は、総合評価で高得点になる可能性もあります。
ひとつの結果にとらわれず、“次に向けてどうするか”を考えることが前向きな第一歩です。
まとめ
シャトルランは、多くの人が「学生時代にイヤだった思い出」として語る種目かもしれません。しかしこの記事を通じて、ただ“しんどいだけ”の運動ではなく、科学的にも非常に優れた体力測定法であること、そして誰でも記録を伸ばせる可能性があることを知っていただけたのではないでしょうか。
本記事では以下のような観点から、シャトルランを多角的に掘り下げてきました:
- シャトルランとはどんな目的をもった体力テストなのか
- 最新データから見る年齢・性別ごとの平均回数
- 自分の記録が全国的にどの位置にあるのか
- 科学的根拠に基づいた記録向上の戦略
- 年齢や目的別のトレーニングの工夫
- 世界のトリビアや“あるある”で楽しく学ぶ
- 他の体力テストとの違いや、自分に合った測定の選び方
そして何より大切なのは、記録の良し悪しよりも「自分がどう変化したか」を大切にすることです。
シャトルランは、音に合わせてただ走るだけに見えて、実は人間の「心肺機能」「瞬発的な持久力」「反応速度」「集中力」など多くの能力を一気に測ることができる総合力テストです。これは、マラソンやリフティングのように単一の能力を測るのではなく、“複数の運動能力を融合して試される”という非常に特異で、かつ教育的な価値の高い種目でもあります。
記録が伸びないときは、「ペースが早すぎた?」「水分は足りてた?」「音に集中できた?」など、振り返るポイントがたくさんあります。そこから“改善”に繋げられる人こそ、本当の意味で体力を育てている人です。
そして、これは学生だけに限りません。社会人になっても、シャトルラン的な要素(集中力、持続力、切り替え力)は、日常生活や仕事の中でも十分に応用されます。だからこそ、学校を卒業してからも“自分の体力と向き合う機会”として、こうした測定が見直されるべき時代に来ているのかもしれません。
また、最新の研究では「持久力が高い人は脳の老化が遅い」「有酸素運動はストレス耐性を高める」といった知見も明らかになっています。つまり、シャトルランに取り組むことは、体力アップにとどまらず、メンタルの強化や将来の健康寿命の延伸にも関わってくるということです。
最後にもう一度強調したいのは、あなたの“今の記録”は未来の可能性にすぎないということ。過去の結果にとらわれず、数ヶ月後・数年後の“成長した自分”を思い描いて、少しずつ歩んでいきましょう。
たった20mの折り返しが、あなたの人生を変えるきっかけになるかもしれません。
シャトルランとは、音に合わせて走るテストではなく、「自分と向き合うトレーニング」なのです。
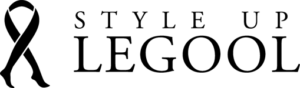



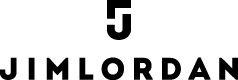





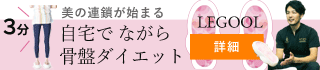
コメント